【専門家監修】売上を上げるための行動経済学23選を徹底解説!
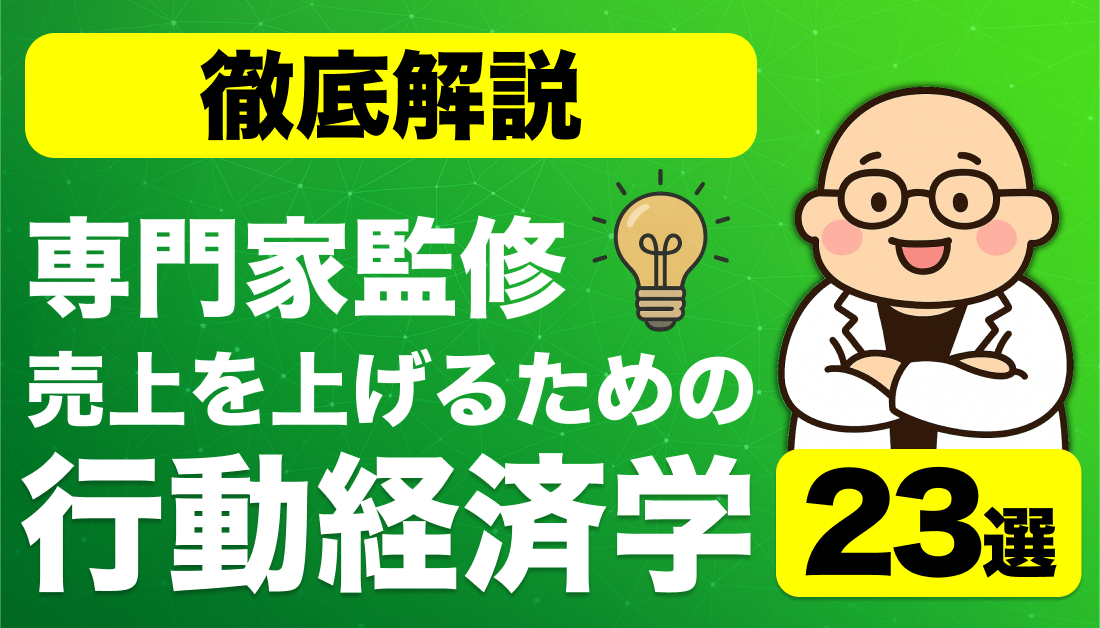
どんな方でも自分で始めたビジネスで、成功を勝ち取りたいと思うでしょう。しかしこれだけ経済が発達し、ライバルが多い現代社会では「無策」で売上を上げることは不可能に近いです。
そこで今回の記事では、売上を上げるための行動経済学を、誰にでも分かりやすくご紹介していきます。
行動経済学をスタートさせたビジネスに取り入れることで、売上が上がることは間違いありません。
こちらでご紹介する行動経済学は、基礎中の基礎のことばかりなので、取り入れていないと絶対に売上が上がらないとも言い切れます。
本記事を読んで頂くことで、基本の行動経済学について理解が深まり自社のビジネスの売上を上げることにつながるでしょう。
行動経済学を取り入れる際の注意点もまとめているので、最後まで読んでみてください。
行動経済学とはなに?
行動経済学とは、人間の心理学を基に現代経済を分析する学問になります。
従来の経済学は、「人は合理的に行動すること」をベースに考えられていますが、行動経済学は逆に「人は合理的に行動しない」という考えをベースに発展した経済学です。
20世紀後半からアメリカを中心に広がり始め、今では世界中の国でマーケティングの基礎としてビジネスに取り入れられています。
ノーベル経済学賞を受賞したイスラエル出身の、ダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーが行動経済学の基礎理論を提唱したと言われています。
売上を上げるには行動経済学が必須な理由
売上を上げるには、行動経済学を学ぶのが必須です。
どうして行動経済学が必須なのか、3つのポイントを挙げてみました。
・売上を上げる為の根底にあるのは人の考え方だから
・人の脳みそが考えることはほとんど一緒だから
・特に店舗経営をする際は行動経済学の効果が分かりやすいから
それぞれのポイントを、詳しく解説していきます。
売上を上げる為の根底にあるのは人の考え方だから
売上を上げるためには、行動経済学を学んだほうがいい理由としては、「売り上げの根底にあるのは、人の考え方だから」ということです。
行動経済学には、人が無意識的にやっている行動の基本がたくさん詰まっています。
従来の経済学とは違い、人間の無意識領域での行動に特化した学問なので人間の根底の考え方にダイレクトにアプローチ出来るのです。
行動経済学を正しく学んで、人の考え方の習性を売り上げアップに繋げてみましょう。
人の脳みそが考えることはほとんど一緒だから
世の中の人の見た目は大きく異なりますが、ほとんどの人の脳みそが考えることは一緒です。
人によって視覚や聴覚からの受け取り方に若干の違いはあっても根底の感覚は一緒なので、人間の無意識領域に訴えかける行動経済学は売上を上げるために学んでおくべきでしょう。
行動経済学を学んで知識を取り入れ、行動を変えることで世の中の多くの人の心に訴えかけるビジネスを出来るようになります。
全ての人には当てはまらないかもしれませんが、統計的には多くの人の感覚に当てはまります。
ビジネスに活用するだけで、成功確率が上がるのです。
同じように挑戦して高い確率で成功したいのであれば、行動経済学は必ず学んでおきましょう。
ちなみに実店舗経営でも行動経済学は売上アップに役立ちますが、インターネットを通じたビジネスでも役立つ要素が満載なので、店舗を持つ予定がない方も必ず行動経済学を学んでください。
特に店舗経営をする際は行動経済学の効果が分かりやすいから
売上を上げるために行動経済学を学んだほうがいい理由の3つ目は、店舗を持って経営する場合は行動経済学の効果が分かりやすいからです。
前述した通りインターネットを使ったビジネスでも行動経済学を取り入れれば、ある程度の売上アップ効果は期待出来ます。
しかし実店舗を構えたビジネスの場合であれば、さらに行動経済学の効果は表れやすくなっています。
実際にお客様と売り場を通じてリアルに繋がれるので、視覚聴覚に訴えかける情報量が多い為です。
ほとんどの人の思考に当てはまっている行動経済学なので、来店された多くのお客様の心を動かせるでしょう。
これから実店舗経営を行って、何らかのビジネスをしようと思っている人は必見の経済学になります。
【専門家監修】売上を上げるための行動経済学23選
では具体的に売上を上げるための行動経済学には、どんなものがあるのか。
行動経済学の基礎の中から誰でも始められる23個の戦略を選んできました。
この行動経済学の基礎を自社のビジネスに取り入れ、売上を上げていきましょう。
ちなみに実際に店舗経営されていて、既にやっているという方は再度目を通していただき、チェックリスト代わりに活用してください。
よくある失敗例としては、「やっていたのに、効果を実証せずに辞めてしまい売上が下がってしまう」パターンです。
再度自社の取り組みを振り返ってみて、店舗経営に生かしていきましょう。
①感覚誘導の照明
売上を上げるための行動経済学1つ目は、感覚誘導の照明です。
店舗経営をして売上を上げるためには、店内の照明を工夫するのがとても重要になります。
人間の無意識的感覚では、照明の色でこんな違いがあるのです。
| 蛍光灯などの寒色系の照明 | 視覚に刺激が強いので、長時間滞在したくなくなる |
| 白熱電球などの暖色系の照明 | 視覚からのリラックス効果があるので、長時間滞在したくなる |
このような感じで、蛍光灯などの白っぽい色の照明を店内に使えば人は視覚からの刺激を強く受けるので、どうしても短時間で退店してしまうのです。
逆に白熱電球のような、温かみのある暖色系の照明を多く使えば人の脳をリラックスさせる効果が期待出来、不思議と店内に長時間滞在してしまいます。
「アパレルショップ」「カフェ」「居酒屋」などの、長時間滞在してもらった方が売上が上がりやすい店舗であれば暖色系の照明を選びましょう。
逆に「立ち食いソバ」などの短時間で退店してもらった方が、回転が高まって売上が上がるようなお店は寒色系の照明がおすすめです。
②視覚的中心の設置
売上を上げるための行動経済学2つ目は、視覚的中心の設置です。
ほとんどの小売店に行くと、店頭の一番目立つところには「目玉商品」が置いてあります。
なぜなら、店頭の目立つところに注目を浴びやすい商品を置いておくことで、人はお店に興味を示して来店するからです。
来店するとその周りに陳列されている商品にも、興味を持って見るのが普通でしょう。
店舗経営で売上を上げたいのであれば、店頭に視覚的中心になる商品を置くのが必須です。
必ず自店の注目商品や売れ筋商品を見つけ出して、目立つ場所に配置しましょう。
もし時点にそういった商品がないのであれば、創り出して陳列しないと売上は下がる一方です。
③パッケージを重たく
売上を上げるための行動経済学3つ目は、パッケージを重たくすることです。
人間の脳は「重たいもの=高級なもの」と錯覚するように出来ています。
例えば、金や銀は重たいもので、不思議と価値があるものだと誰もが共通認識しますよね。
鉄なども重たいものなので、なんとなく触ると価値がある様な錯覚を起こします。
その他、重たくすることで「価値がある」と勘違いさせているものを挙げてみました。
- 厚紙で作った名刺、金属で作った名刺
- 底の瓶の部分を厚くしたワインのボトル
- ブランドショップの紙袋
このように、軽いパッケージにも出来るのに敢えて重みのあるパッケージにすることで消費者に「高級なものだ、大切にしなければ」と錯覚させることが出来ます。
捨てずに長時間持っておいてもらいやすいので、人間の意識にも商品名やお店の名前が残りやすいのです。
④ヒューリスティック誘導
売上を上げるための行動経済学4つ目は、ヒューリスティック誘導です。
ヒューリスティック誘導とは「人の脳は指示を出したらその通りに行動してくれる」という現象を応用したマーケティングになります。
分かりやすい例としては、お店に行くと「おすすめ№1、№2、№3」などのPOPが掲示されていたりしますが、それがヒューリスティック誘導です。
お店に来店して自分がどの商品を買えばいいのか決められなかった場合、人は不思議と「おすすめ」と掲示されている商品を購入する傾向があります。
決められない時は、POPに誘導されてしまうのです。
またそうしたおすすめPOPなどの掲示が明確なお店は、お客様の回遊率や滞在時間が長くなる傾向もあります。
自社の店舗にこうしたPOPが付いていないのであれば、すぐに掲示するようにした方が売上は上がるでしょう。
⑤BGMのテンポ
売上を上げるための行動経済学5つ目は、BGMのテンポです。
人間は流れているBGMから無意識的に、多くの影響を受けています。
BGMのテンポによってどんな違いがあるのかを、簡単に表にまとめてみました。
| テンポの速いBGM | 落ち着かない感覚になるので、お客様の店内滞在時間が短くなる |
| クラシックなどのテンポのゆったりしたBGM | リラックスする効果があるので、お客様の店内滞在時間が長くなる |
BGMのテンポは、お客様の店内滞在時間に影響します。
お客様の回転を早くしたい場合は、アップテンポのBGMを流せばいいですし、逆にゆっくり店内に滞在してもらいたい場合はゆっくりしたテンポのBGMを流すと効果的でしょう。
飲食店などではランチの忙しい時間はアップテンポのBGMにして、それ以外の落ち着いた時間帯はゆったりテンポのBGMに変えるのもありです。
⑥限定性の強調
売上を上げるための行動経済学6つ目は、限定性の強調です。
店舗経営をしていて商品やサービスの回転を上げたいのであれば、限定性の強調は必須項目になります。
限定性の強調には、以下のような例があります。
- 在庫残り○○個
- 1日○○食限定
- 〇月期間限定販売
このような感じで限定性を持たせることで、人は「早く購入しないと無くなってしまう」という気持ちにさせられて、急いで商品を買ったりサービスを受けたりします。
仮に売れ残っている商品だったとしても、「残り限定○○個」とPOPを付けるだけで、人気商品に変えることも出来るでしょう。
本屋さんの特設コーナーで商品を打ち出したりする場合は、ボリュームを持って商品陳列した方がいいですが、個人で商品を売り出すのであれば、数量を絞って限定的に魅せた方が価値が高まって販売に繋がります。
⑦香りの誘導
売上を上げる行動経済学の7つ目は、香りの誘導です。
出来ることであれば、お店の特色の香りはなるべくお客様に届くようにアピールしましょう。
香りの誘導の事例で最も分かりやすいのが、パン屋さんの香りです。
パン屋さんは焼きあがったパンの香りを、必ず人通りが多い場所にダクトを設置して多くの人に嗅いでもらいやすくしています。
人間の5感の中で最も敏感なのは嗅覚だとも言われているほど、香りが人間の直感に与える影響力は強いのです。
だから、自社の商品でいい香りのものはなるべく多くの方に匂ってもらいやすいようにしましょう。
自社の会社の「イメージの匂い」を作るのも、ブランド戦略の1つになります。
⑧対比の利用
売上を上げるための行動経済学8個目は、対比の利用です。
店舗経営をしていて売上を上げたいのであれば、必ず「超高級な商品」を1つは置くようにしましょう。
ほとんど売れないけれど、高級な商品をお客様から見える場所に展示するのはとても効果的です。
なぜなら、人はいくつかの価格帯の中から商品を選びたいからです。
また対比を利用することで、購入1品単価を上げる効果も期待出来ます。
- 一番高級な5,000万円のワインを用意する
- 本当は5万円のワインしか飲みたくない人が来店する
- 5,000万円のワインがあるので不思議と20万円くらいのワインが安く感じる
- 見栄もあるので、5万円のワインではなく、20万円のワインを購入してくれる
このような感じで、人は何かを何かを比べるタイミングで物の価値を決めたりするのです。
価格の比較をしてもらう為にも、無駄でも高級な商材は陳列するようにしましょう。
⑨ミラーニューロンの刺激
売上を上げる行動経済学の9個目は、ミラーニューロンの刺激です。
人は目の前にいる人がやっていることを、そのまま鏡写しの様に脳の中にイメージする特性があります。
心理学などで目の前にいる人と、同じ動きをいつの間にかするようになるとよく言われますが、その効果は店舗経営でも役立つのです。
例えばビールを販売したい場合、ビールをただ缶や瓶の状態で陳列するだけではなく、美味しそうに飲んでいる動画を流せばビールの購買率は高まります。
つまり動画を通じて、商品を使っているところが脳内でイメージされるので、その感覚を得た人が購入したくなってしまうのです。
アパレルショップなどでは、洋服を着せたポスターやトルソーなどが置いてあると購入したくなりますよね。
⑩プライミング効果
売上を上げる行動経済学の10個目は、プライミング効果です。
プライミング効果とは、その商品やサービスを購入した後のイメージをお客様に持たせ、購入を促していく施策になります。
例えばスーパーに行くと、「玉ねぎ」「人参」が陳列してあり、その先には「ジャガイモ」がある。
さらに進むと「今日はお肉の特売日です」と打ち出しがきて、目の前に「カレーのルウ」が大量陳列されている。
こんなコーナーになっていたら、多くの人はカレーのコーナーに行く前に既になんとなくカレーを食べたい気分になっているでしょう。
これが、プライミング効果を使ったマーケティングの1例になります。
人間はお金を使って購入した商品を使って、どうなりたいのか?をイメージして買うか買わないかを決めます。
プライミング効果を利用すると、そうしたイメージをより具体的にお客様に植え付けやすくなるのです。
⑪サンプルコーナー
売上を上げる行動経済学、11個目はサンプルコーナーです。
多くの店舗型のビジネスをされている方は、既に取り入れられていると思いますが、サンプルコーナーがあるか無いかで、商品やサービスの購入率は格段に変わります。
「美味しい商品」と書かれても、実際に食べてみなければ本当に美味しいのかどうかが分からないので、人はリスクを冒して買わないのです。
化粧品や枕などであれば、実際に体にテストしたりしなければ購入を躊躇する場合も多いでしょう。
店舗経営で商売をするのであれば、ほとんど100%のことがサンプル可能だと思うので、出来る限りお店中に取り入れてください。
⑫色彩心理学
売上を上げる行動経済学の12個目は、色彩心理学です。
購入してもらいたい商品のカラーは、赤やオレンジなどの色にしましょう。
人間は赤やオレンジなどのカラーを見ると、「早く買わないと」という感覚になるように出来ています。
逆に青や緑のカラーにすると、リラックスして商品を購入しにくくなっているのです。
店内で特に購入してもらいたい商品には、赤やオレンジ、黄色などのPOPを付けて訴求しますが、それはそのためだったのです。
赤やオレンジのカラーを見ると、人間は冷静な判断力を失ってしまいます。
冷静な判断力が低下すると、今買わないといけないという気持ちになってついつい購入してしまうのです。
もしお客様に長時間くつろいでほしいのであれば、壁紙を青や緑のカラーで統一するといいでしょう。
ホテルのフロアなどは、ところどころにグリーンを使い、落ち着いた雰囲気にしてあることが多いですね。
⑬好奇心の刺激
売上を上げる行動経済学の13個目は、好奇心の刺激です。
例えばお店の陳列棚のスペースに、「売り切れました」「次回入荷予定〇月〇日」などのPOPを掲示しておく方法になります。
通常のお店であれば空いたスペースはもったいないので、別の商品の売り場を広げて少しでも利益に繋げようとします。
ただいつでも商品がある状態だと、お客様は好奇心を刺激されません。
人間の好奇心を刺激するためにも、こうした「入荷待ち」などのPOPの掲示は効果的なのです。
店内全ての商品にする必要は無く特定の商品にだけこうした展開をしていれば、お客様の商品に対する興味関心が高まるでしょう。
飲食店であれば、「次回新作は〇月〇日にスタート」などとアピールすると、その日に合わせてお客様が来店してくれます。
⑭視線誘導ディスプレイ
売上を上げる行動経済学の14個目は、視線誘導ディスプレイになります。
視線誘導ディスプレイとは簡単に言うと、「売り場の配置」のことですね。
利益率が高く出来るだけ数を売りたいと思っている商品は、人の目線の高さに置くのが普通です。
一方でお客様が探してでも欲しいと感じるけれど、ニッチな需要の商品は誰でもお店の棚の下の方に陳列します。
そうやって人間の無意識レベルの視覚の癖を利用したのが、視線誘導ディスプレイになります。
売り場を作る際の基礎にもなる戦略なので、全く考えていない場合はすぐに売り場を見直す必要があるでしょう。
⑮リピートのためのサンクスカード
リピートのためのサンクスカードを贈ることも、売上を上げる行動経済学の1つです。
一度利用して下さったお客様に、きちんとサンクスカードを送ったり、次回来店を促す工夫をしているでしょうか?
サンクスカードなどのアプローチをしなければお客様からお店の記憶は薄れてしまい、再来店には繋がりにくくなります。
全てのお客様には難しいかもしれませんが、大量購入してくれたお客様や高額品を購入して下さったお客様には、必ずサンクスカードを贈るべきです。
ちなみにサンクスカードは事前に準備した物や、事前に印刷したものだと効果は薄くなります。
超優良なお客様には、その場で名刺などに担当者が「手書きで」感謝のメッセージを書きましょう。
その場で手書きで書く事で、お客様とリアル感を共有することが出来ます。
この体験を通じてお客様は、好印象を持って次回も利用しようと思ってくれるのです。
⑯セット販売
売上を上げるための行動経済学16個目は、セット販売です。
非常に当たり前の話で、ほぼ100%の方が自社の店舗に取り入れられていると思いますが、基本に立ち返ってもう一度確認して頂きたいポイントです。
本当にセットで利用するものが、売り場の隣同士に陳列されているでしょうか?
セット販売される実例としては、以下のようなものがあります。
- カレーのルウとニンジンやジャガイモ
- 剃刀の横にシェービングクリーム
- フライドチキンの横にケーキ
このような感じで、売り場を見てお客様が物語を感じられるセット販売売り場になっていないと、売上は上がりません。
非常に基本的なことなので、何度も基本に立ち返って売り場構成を見直してみてください。
セットで購入すると割引があるような施策も、セット販売の常套手段ですね。
⑰店内ミラー
店内にミラーを設置することも、売上を上げる行動経済学の1つです。
店内にミラーを設置することで、お客様の自意識が高まり購買意欲が高まる効果が期待出来ます。
- アパレルショップでは商品を当てて着用イメージが湧く
- 鏡があることで自分の姿が確認出来て「もっと美しく」という欲を掻き立てる
- 高級品を扱っているお店では周りから見られているという意識で見栄っ張りになる
このような感じで店内にミラーを配置するだけで、人間の根底にある自意識に働きかけて、もっと良くなりたいという意識を倍増させる効果があります。
高級品を扱っているお店では、ミラーの設置が必須なので自社の店舗を見直してみましょう。
ちなみに、飲食店ではミラーの設置で食欲減退が起こってしまうのでおすすめしません。
⑱過去データ→パーソナライゼーション
行動経済学を使って売上を上げるのであれば、過去データからのパーソナライゼーションを導入するのも必須です。
簡単に言うと「以前お客様が何を購入されて、それをきちんとデータとして残して共有しているか?」ということになります。
前回の来店で商品を購入して下さったお客様には、その商品と相性のいい商品を勧めるのが普通です。
しかしデータを残していなければ、お客様へちぐはぐな商品をおすすめしてしまうので継続しての販売に繋がりにくいでしょう。
毎年買って下さるお客様に、「今年もいかがですか?」というアプローチをするのも、パーソナライゼーションの1つです。
⑲安心感を与える接客
売上を上げる行動経済学の19個目は、安心感を与える接客です。
接客には様々なスタイルがあります。
- こちらからどんどんおすすめ商品を勧める接客
- 来店時に声掛けをしていつでも質問してもらいやすい状態にする接客
いずれの方法にしても、スタッフが安心してお客様に寄り添ってくれるという安心感を与えることが、売上増加に繋がります。
最悪なのは入店しても誰も声をかけて来ず、お客様を無視してしまう状態でしょう。
⑳「待つこと」への価値付け
売上を上げるための行動経済学20個目は、待つことへの価値付けです。
基本的に人は自分のペースを乱されたくないので、待ち時間を嫌います。
それがお金を払って手に入れたサービスであれば、さらに腹立たしく感じる人も多いでしょう。
そんな時に「待ち時間も楽しく出来る工夫」があれば、一気にお客様の満足度は高まります。
例えば、ディズニーランドなどでは1時間待ちが当たり前のアトラクションばかりですが、その待ち時間も建物の建て方やアトラクションを楽しまれている方のリアクションなどでワクワクを感じてもらえるようになっているのです。
待ち時間は誰もが苦痛に感じる時間ですが、創意工夫を取り入れて待ち時間も「ワクワクしてもらえる」環境を整えましょう。
㉑丸くする戦略
売上を上げるための行動経済学21個目は、丸くする戦略です。
人間は尖っているものに恐怖を感じ、丸くなったものに安心を感じるような特性があります。
なので、丸くすることでお客様の滞在時間を長くする効果があるのです。
- スーパーの売り場の角を丸くしたことで親子連れのお客様の滞在時間が長くなった
- お店の入り口を丸くしたことで来店客数が増加した
丸くする戦略で、このような効果が現れた事例があるのであらゆるものを丸くしてみる戦略はおすすめです。
ちなみにお客様の滞在時間を短くしたいお店は、店内の物を四角く統一すると滞在時間が短くなります。
㉒レッドテープ、カーペット
売上を上げるための行動経済学22個目は、レッドテープ&カーペットです。
お店に行列を作りたいのであれば、お店の店頭やお客様に並んでいただきたい場所にレッドテープやカーペットを配置すると、効果的です。
仮にそこまで繁盛していないお店であっても、「こちらにお並び下さい」というようなシートを貼るだけで、人はそこに並びたくなってしまいます。
こうしたテープやカーペットを貼るだけで、入店客が増えるともされているので来店客を増やしたい方にはおすすめの戦略です。
㉓BBB戦略
売上を上げるための行動経済学、最後の23個目は「BBB戦略」です。
BBB戦略とは以下のものを、PRキャラクターに使いましょうという戦略になります。
- Beauty(美女)
- Beast(動物)
- Baby(赤ちゃん)
これらの要素のあるキャラクターをPRに使うだけで、お客様の印象に強烈に残るのでお店のことを覚えてもらいやすくなります。
SNSなどでも犬猫の動画や赤ちゃんの動画は爆発的にインプレッションされていますが、それはそのためです。
売上を上げるための行動経済学をする際の注意点
売上を上げるための行動経済学を取り入れる際に、必ず注意してもらいたいことを3点挙げてみました。
- 限定性は必ず押さえる
- 店舗によってやり方が変わる
- 看板をバカにしない
それぞれ簡単に解説していきましょう。
限定性は必ず押さえる
今回ご紹介した行動経済学の中でも、売上を上げるために絶対に取り入れてもらいたいのは「限定性」です。
商品やサービスに限定性を持たせて、お客様に「買う理由」を感じてもらうことがビジネスの場では非常に重要になります。
もし23個の項目を全て網羅するのが難しいと思われるのであれば、自社の提供している商品やサービスに必ず「限定性」を持たせてみましょう。
「ここで買わないと後悔する」という気持ちをお客様に植えつけられれば、成功です。
店舗によってやり方が変わる
売上を上げるために行動経済学を導入する際は、店舗によってやり方が異なることを知っておきましょう。
高級品を扱っているお店で、回転率を上げる戦略をしても無意味ですし、回転を上げたい大衆的なお店で高級路線の戦略をしても効果はありません。
自社のサービスがどんな方に向けたサービスなのか、ペルソナをはっきりさせて取り入れてください。
看板をバカにしない
行動経済学を学んで売り場に取り入れるのは必須ですが、さらにおすすめなのは「看板を有効活用すること」です。
看板は意外と人の目に留まり、入店するか否かのきっかけ作りになります。
店内をイメージさせて入店を促す看板でもいいですし、店舗名を大きく掲載してネット検索してもらう目的の看板でもありです。
どんな看板の使い方がいいのかは店舗のスタイルによって異なりますが、行動経済学を売り場に取り入れるのと同じくらいに看板は重要でしょう。
売上を上げる行動経済学のまとめ
今回は売上を上げるための行動経済学23選と言うことで、記事をまとめてきました。
行動経済学を店舗経営やネットビジネスに取り入れることで、お客様やユーザーからの反応は大きく変わります。
もう一度記事を振り返って頂き、本当に自社の店舗に導入されているか、もしくはこれから出店するお店に取り入れられそうかを再度確認してみましょう。
▼YouTubeでも解説しています。
【超有料級】脳科学の専門家が語る、コレをやっていない店舗は儲からない!成果・売上をあげるための行動経済学23選
https://youtu.be/4HBvSv8OS0I?si=5F3ylYG6z4Gc0UI9
次世代マーケティング戦略を無料プレゼント
この記事をお読みいただいた方へ、期間限定の特典をご用意しました。公式LINEにご登録いただくと、以下の豪華特典(すべて無料)を今すぐお受け取りいただけます。
- 「人の心理とビジネスを10年以上研究しつづけた結果 成功するビジネスの作り方まとめ」(動画)
- 「AIに勝てるニューロマーケティング本」(PDF)
- 「私があなただけに教えるAIを使ってマーケティングする方法」(PDF)
- 「黒字から始めるマーケティングのやり方」(PDF)
どれも、経営者やマーケターの皆様にとって明日から実践できるヒントが満載のコンテンツです。LINE登録はわずか30秒で完了しますので、ぜひ友だち登録して特典をお受け取りください!成功するビジネスへのヒントを詰め込んだ資料と動画を手に、新たなマーケティング施策に踏み出してみましょう。
継続的に顧客の心と脳を研究し、賢く脳科学を活用することで、きっとあなたのマーケティングも次のステージへと進むはずです。ぜひこの機会にニューロマーケティングの第一歩を踏み出してください。


法廷臨床心理学博士・ニューロマーケティング(脳科学マーケティング)トレーナー
株式会社ビジネスサイエンスジャパン取締役。ビジネスサイエンストレーニングアカデミー学長。
1985年東京都文京区生まれ。神奈川県横浜市のサン・モール・インターナショナル・スクールの高校を卒業。
2006年米国オレゴン州ルイス&クラーク大学にて心理学専攻及び中国語を副専攻で大学卒業。
2008年米国フロリダ州アルビズ大学大学院にて心理学修士課程修了。
2013年同大学院臨床心理学博士号、法廷特化で卒業(博士論文Doctoral Project:Endo, T. K. (2012) Test Construction: Clinician’s Gay Male Competence Inventory. (Doctoral dissertation, Carlos Albizu University)。後、オレゴン州にて臨床心理学者の国家治療免状を獲得。マイアミ市警、FBI、CIAの調査支援を行った実績を持つ。
2017年には薬物依存人口を減らした功績を称えられ、2017年フロリダ州ジュピター市より表彰される(2017 Best of Jupiter Awards - Drug Abuse & Addiction Center)。現在は実践的ビジネスサイエンス、実践的心理学、脳科学的教育、ニューロマーケティングの普及、後進の育成に努める。著書に『売れるまでの時間-残り39秒 脳が断れない「無敵のセールスシステム」』(きずな出版)、共著に『仕事の教科書』(徳間書店)がある。


