意思決定バイアスに騙されるな!管理職が陥る心理トラップ5選
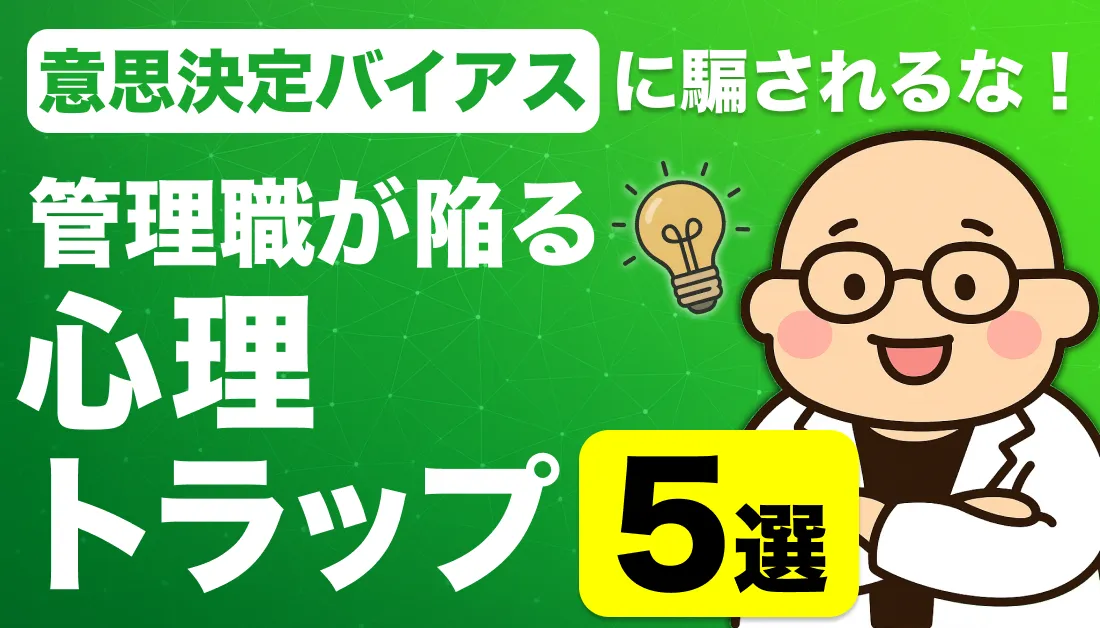
はじめに:なぜ“論理的なはずの管理職”が判断を誤るのか?
管理職やリーダーは、日々大小さまざまな意思決定に迫られています。人材採用、戦略変更、取引判断など──判断力がビジネス成果を左右する場面は多いでしょう。
ところが、論理的に考えているつもりでも、実際には「感情」や「無意識の偏り(バイアス)」によって判断が歪められているケースが非常に多いのです。これは個人の資質の問題ではなく、人間の脳の“仕様”とも言えます。
遠藤貴則博士(行動経済学・意思決定研究)の視点を借りながら、今回は「管理職が無意識に陥りやすい意思決定バイアス5選」とその対策を紹介していきます。
バイアス1:アンカリング効果|最初に見た情報に縛られる
「前任者は1000万円で契約していたから、うちもそのくらいが妥当だろう」
これはアンカリング(Anchoring)という典型的な認知バイアスです。人は最初に提示された数字や情報に強く影響され、それを基準として以後の判断を下してしまいます。
対策:複数の視点・相場から判断する
- 他社事例、過去の実績、顧客ニーズの3軸で比較検討する
- 最初の「アンカー」が妥当かどうかを常に疑う姿勢を持つ
バイアス2:確証バイアス|自分の信じたい情報ばかり集める
「やっぱりうちの方向性で間違ってなかった。そう書いてある記事もあったし」
確証バイアスとは、自分の仮説や意見を裏付ける情報ばかりを探してしまい、反証となるデータを無視する心理です。
対策:意識的に“逆の立場”の意見を取り入れる
- ディベート方式の会議を取り入れる
- 第三者レビューを受ける文化をつくる
バイアス3:正常性バイアス|「まあ大丈夫だろう」の慢心
「市場の変化?うちはこれまで通りでやっていけるよ」
危機や変化に対して「自分は大丈夫」「まだ何とかなる」と思い込む心理的防衛反応。特に経験値の高い管理職ほど陥りやすい。
対策:定期的な“変化チェック”と意思決定フレームを導入
- 四半期ごとの「変化レビュー会議」などを設ける
- 「最悪のシナリオ」をあえて想定し、チームで議論する
バイアス4:現在バイアス|目先の利益を優先してしまう
「今月の売上がまずいから、とりあえずキャンペーンやっちゃおう」
短期的な成果を優先しすぎることで、中長期のブランド価値や信頼を損なう可能性がある意思決定です。
対策:中長期の目的とセットで判断軸を持つ
- 「短期・中期・長期」視点での意思決定フレームを導入
- KPIと合わせて“LTV(顧客生涯価値)”も常に併記する
バイアス5:損失回避バイアス|損を避けるためにチャレンジを避ける
「今やっている施策をやめるのはもったいないから、もう少し様子を見よう」
人は「得をすること」よりも「損を避けること」に強く反応します。これにより、明らかに効果のない戦略を“継続”してしまうことが多発します。
対策:数字と事実で継続判断を行う仕組み化
- 毎月の定例で「やめるべきこと会議」を行う
- 感情ではなく、効果指標・成果率で継続/撤退を判断する
遠藤貴則からの提言|バイアスを“消す”のではなく“環境で整える”
人はバイアスから逃れられません。でも、判断がズレにくい“環境”は設計できます。
つまり、個人の努力でバイアスをゼロにすることは不可能でも、組織として「バイアスに強い環境=思考のクセに気づける構造」を整えることは可能だということ。
これは、ナッジ理論や行動経済学の基本的なアプローチでもあります。「行動を変えるには、仕組みを変える」──管理職にとってこそ最も必要な視点です。
まとめ:バイアスを理解することが“最強のリスクヘッジ”になる
意思決定ミスは、経営にとって最大のコストになり得ます。
しかし、「自分もバイアスにかかっているかもしれない」と気づき、チェックリストやフレームで環境を整えておくだけで、判断の精度は劇的に上がります。
あなた自身、そしてあなたのチームの意思決定を守るために、まずはこの5つのバイアスを“意識すること”から始めてみてください。
次世代マーケティング戦略を無料プレゼント
この記事をお読みいただいた方へ、期間限定の特典をご用意しました。公式LINEにご登録いただくと、以下の豪華特典(すべて無料)を今すぐお受け取りいただけます。
- 「人の心理とビジネスを10年以上研究しつづけた結果 成功するビジネスの作り方まとめ」(動画)
- 「AIに勝てるニューロマーケティング本」(PDF)
- 「私があなただけに教えるAIを使ってマーケティングする方法」(PDF)
- 「黒字から始めるマーケティングのやり方」(PDF)
どれも、経営者やマーケターの皆様にとって明日から実践できるヒントが満載のコンテンツです。LINE登録はわずか30秒で完了しますので、ぜひ友だち登録して特典をお受け取りください!成功するビジネスへのヒントを詰め込んだ資料と動画を手に、新たなマーケティング施策に踏み出してみましょう。
継続的に顧客の心と脳を研究し、賢く脳科学を活用することで、きっとあなたのマーケティングも次のステージへと進むはずです。ぜひこの機会にニューロマーケティングの第一歩を踏み出してください。


法廷臨床心理学博士・ニューロマーケティング(脳科学マーケティング)トレーナー
株式会社ビジネスサイエンスジャパン取締役。ビジネスサイエンストレーニングアカデミー学長。
1985年東京都文京区生まれ。神奈川県横浜市のサン・モール・インターナショナル・スクールの高校を卒業。
2006年米国オレゴン州ルイス&クラーク大学にて心理学専攻及び中国語を副専攻で大学卒業。
2008年米国フロリダ州アルビズ大学大学院にて心理学修士課程修了。
2013年同大学院臨床心理学博士号、法廷特化で卒業(博士論文Doctoral Project:Endo, T. K. (2012) Test Construction: Clinician’s Gay Male Competence Inventory. (Doctoral dissertation, Carlos Albizu University)。後、オレゴン州にて臨床心理学者の国家治療免状を獲得。マイアミ市警、FBI、CIAの調査支援を行った実績を持つ。
2017年には薬物依存人口を減らした功績を称えられ、2017年フロリダ州ジュピター市より表彰される(2017 Best of Jupiter Awards - Drug Abuse & Addiction Center)。現在は実践的ビジネスサイエンス、実践的心理学、脳科学的教育、ニューロマーケティングの普及、後進の育成に努める。著書に『売れるまでの時間-残り39秒 脳が断れない「無敵のセールスシステム」』(きずな出版)、共著に『仕事の教科書』(徳間書店)がある。


