ちいかわはなぜ流行る?行動経済学を使ったマーケティング術
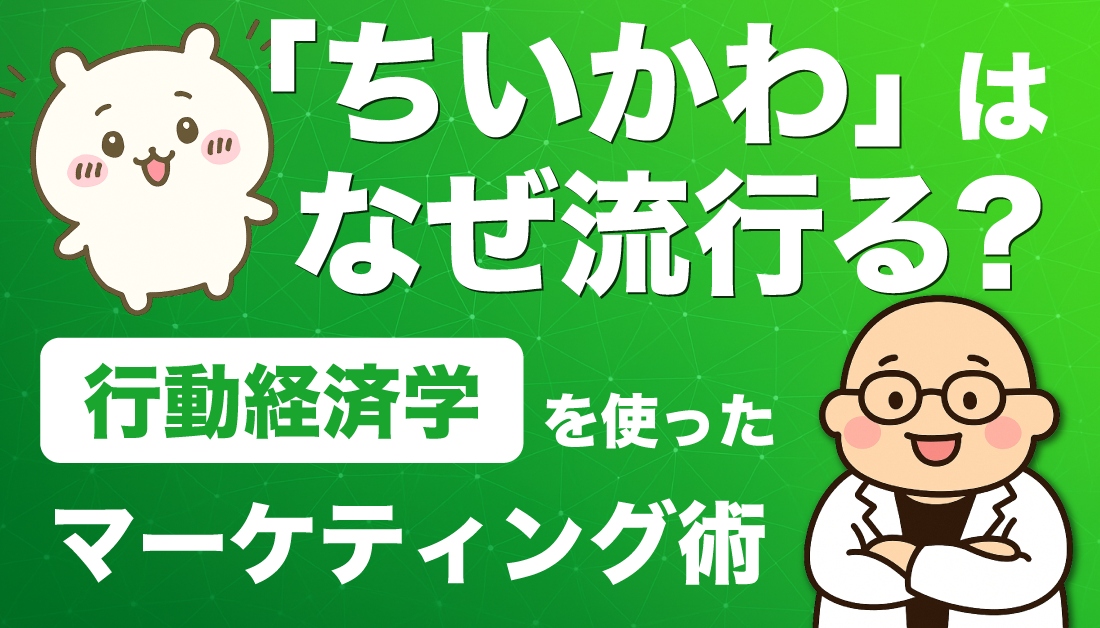
ちいかわがなぜ売れているのか?不思議に思いますよね。
2020年代、SNSから生まれた小さなキャラクターちいかわ(なんか小さくてかわいいやつ)」。その人気は単なる“かわいい”を超え、感情・心理・経済行動の交差点で熱狂的なファン層を形成しました。
ちいかわは今、単なるかわいいに留まらず、日本中の心を掴み、企業マーケティングの在り方まで変え始めています。
本記事では、マーケティングに詳しいビジネスパーソンに、ちいかわブームの背景にある行動経済学の理論に光を当て、なぜここまで人々の心を惹きつけ、財布の紐を緩めるのかを解き明かします。
群衆行動と「みんなが欲しい」心理の爆発力
「ちいかわが、なぜこんなにも売れている???」みなさん不思議に思いますよね。
東京駅のちいかわショップでは、毎週末になると人が通れなくなるほど行列ができています。若い女性を中心に飛ぶように売れるちいかわ。なぜ、こんなにも人気なのか?
ちいかわの人気が爆発的に拡大した背景には、「群衆行動」や「社会的証明」と呼ばれる心理現象が深く関わっています。人は、周囲の行動や評価を参考にし、自分の選択を正当化しようとします。「みんなが買ってる」「行列ができてる」「完売している」という事実そのものが、消費者にとっての“品質保証”となるのです。
SNSでのバズや、抽選倍率20倍といった「可視化された人気」が、人々に「今買わないと損する」「持ってないと乗り遅れる」という焦りを生み出し、ちいかわの需要を連鎖的に膨らませていきました。人気がさらに人気を呼ぶ、この正のスパイラルは、現代のキャラクターIPにおける成長モデルの象徴と言えるでしょう。
癒しと共感に満ちた感情バイアスの魔力
ちいかわは、単なるかわいいマスコットでは終わりません。彼らの物語には、「草むしり検定」に代表されるように、報われない努力や理不尽さが描かれています。そうしたリアルな痛みに直面するキャラたちの姿に、多くの社会人が自分を重ね、「これは私の物語だ」と感じるのです。
このような共感の感情は、行動経済学でいうところの「感情バイアス」を生み出します。感情に訴える体験は、情報よりもずっと深く心に残り、行動を促します。だからこそファンは何度でもグッズを買い、アニメを観て、ちいかわを“推し続ける”のです。癒されながら、どこか切なさや哀愁を抱くちいかわの世界観は、日々のストレスを抱える20〜40代未婚層の心に静かに刺さり続けています。
「逃したくない」が背中を押す、損失回避の心理
限定品やキャンペーンに列をなすファンたち。そこには「FOMO(見逃しへの恐れ)」が強く働いています。行動経済学では、得をするより損を避けたいという「損失回避バイアス」が人の意思決定に大きな影響を与えるとされます。
ちいかわの場合、一度売り切れを経験したファンは、その“失敗”を二度と繰り返したくないという思いから、次回は早朝から並んだり、複数回キャンペーンに参加したりします。企業側もこの心理を巧みに活かし、期間限定・シリーズ展開・コンプリート欲求をくすぐる施策を連発。ちいかわファンは「欲しいから買う」のではなく、「逃したくないから行動する」状態に導かれているのです。
スピード×文脈が生むフレーミング効果の威力
SNS連載からわずか2年でのアニメ化という異例のスピード展開は、ちいかわが話題の鮮度を保ちながら一般層へ浸透した大きな理由です。加えて、企業コラボでは原作のエピソードや世界観に基づいた商品設計がなされ、ファンに「これはあのシーンの再現だ!」と感じさせる工夫が凝らされています。
これは「フレーミング効果」と呼ばれる心理作用で、同じ商品でも“どんな文脈で語られるか”によって受け手の印象や価値判断が大きく変わるというものです。ちいかわの場合、単なるマグカップでさえも、ストーリーと結びつくことで特別な意味を持ち、購買を後押ししています。
20〜40代のSNSユーザー層を掴んだ理由
ちいかわ現象のもう一つのポイントは、その“ハマる人”の属性にあります。特に20〜40代の未婚・SNSヘビーユーザー層が中心で、彼らは情報感度が高く、自分の感情や日常をSNSで表現する傾向があります。
だからこそ、ちいかわのグッズを手にしたり、コラボメニューを食べたりする行動そのものが「推し活」としてSNSに投稿され、拡散されていきます。このようにしてファン自身がマーケティングの担い手となり、熱狂が熱狂を呼ぶ構図ができあがっています。
差別化された世界観と、他キャラにはない共感性
ハローキティやすみっコぐらしといった既存の人気キャラと比べても、ちいかわは異質です。企業発ではなくSNS発の個人作品として登場し、日常の葛藤や苦しみまでもキャラクターのストーリーに盛り込んでいます。こうした“闇”の描写があるからこそ、ファンは単なる消費者ではなく、「共に生きる仲間」としてキャラに愛着を持つのです。
そして、サンリオやサンエックスが“癒しの完成形”を提供するのに対し、ちいかわは“癒しの過程”を見せる存在。そのドラマ性が、「かわいい」を超えて心を打つのです。
まとめ:共感と心理を武器にした新時代のキャラIP
ちいかわの成功は、行動経済学の理論が現実のビジネスにいかに応用され得るかを教えてくれます。「みんなが持ってる」「逃したくない」「自分の気持ちが投影できる」――こうした感情と心理を戦略的に設計し、SNSやコラボを通じて可視化・拡散することで、爆発的な成長が可能になるのです。
マーケターや商品企画者にとっては、ちいかわは単なるキャラ人気の成功例ではありません。ファンのインサイトを理解し、心理に寄り添いながら展開することで、熱量ある支持を作るという示唆に富んでいます。ちいかわの背景にある心理効果と戦略の相乗作用は、あらゆるマーケターや商品企画担当者にとって参考になるはずです。
次世代マーケティング戦略を無料プレゼント
この記事をお読みいただいた方へ、期間限定の特典をご用意しました。公式LINEにご登録いただくと、以下の豪華特典(すべて無料)を今すぐお受け取りいただけます。
- 「人の心理とビジネスを10年以上研究しつづけた結果 成功するビジネスの作り方まとめ」(動画)
- 「AIに勝てるニューロマーケティング本」(PDF)
- 「私があなただけに教えるAIを使ってマーケティングする方法」(PDF)
- 「黒字から始めるマーケティングのやり方」(PDF)
どれも、経営者やマーケターの皆様にとって明日から実践できるヒントが満載のコンテンツです。LINE登録はわずか30秒で完了しますので、ぜひ友だち登録して特典をお受け取りください!成功するビジネスへのヒントを詰め込んだ資料と動画を手に、新たなマーケティング施策に踏み出してみましょう。
継続的に顧客の心と脳を研究し、賢く脳科学を活用することで、きっとあなたのマーケティングも次のステージへと進むはずです。ぜひこの機会にニューロマーケティングの第一歩を踏み出してください。


法廷臨床心理学博士・ニューロマーケティング(脳科学マーケティング)トレーナー
株式会社ビジネスサイエンスジャパン取締役。ビジネスサイエンストレーニングアカデミー学長。
1985年東京都文京区生まれ。神奈川県横浜市のサン・モール・インターナショナル・スクールの高校を卒業。
2006年米国オレゴン州ルイス&クラーク大学にて心理学専攻及び中国語を副専攻で大学卒業。
2008年米国フロリダ州アルビズ大学大学院にて心理学修士課程修了。
2013年同大学院臨床心理学博士号、法廷特化で卒業(博士論文Doctoral Project:Endo, T. K. (2012) Test Construction: Clinician’s Gay Male Competence Inventory. (Doctoral dissertation, Carlos Albizu University)。後、オレゴン州にて臨床心理学者の国家治療免状を獲得。マイアミ市警、FBI、CIAの調査支援を行った実績を持つ。
2017年には薬物依存人口を減らした功績を称えられ、2017年フロリダ州ジュピター市より表彰される(2017 Best of Jupiter Awards - Drug Abuse & Addiction Center)。現在は実践的ビジネスサイエンス、実践的心理学、脳科学的教育、ニューロマーケティングの普及、後進の育成に努める。著書に『売れるまでの時間-残り39秒 脳が断れない「無敵のセールスシステム」』(きずな出版)、共著に『仕事の教科書』(徳間書店)がある。


