行動経済学のナッジを使って、家族をダイエットさせてみよう
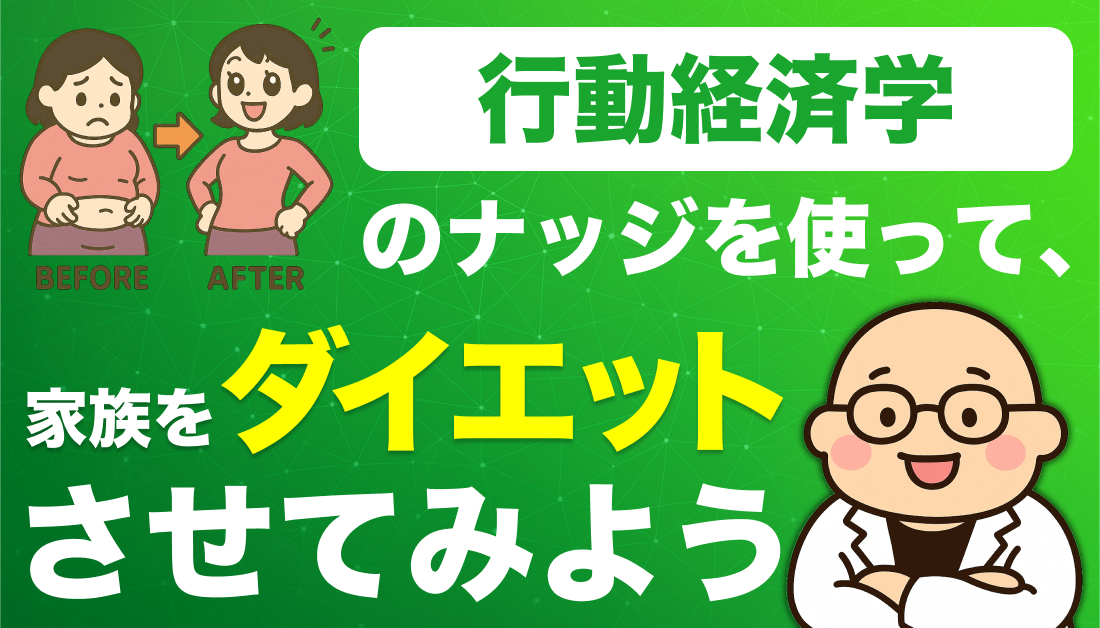
無理なく健康を選びたくなる、「ナッジ」という優しい工夫
日々の暮らしのなかで、「もっと健康的に過ごしたい」と感じる瞬間は誰にでもあるものです。でも、そう思った翌日から急に食生活を改めたり、運動習慣を完璧にこなしたりするのは、現実的にはなかなか難しいものですよね。人の行動は、意志だけで決まるわけではなく、周囲の環境やちょっとしたきっかけにも左右されるものです。
そこで最近注目されているのが、「ナッジ(nudge)」というアプローチです。直訳すれば「そっと背中を押す」という意味を持つこの概念は、選択を強制せずに、自然と望ましい行動を促すための工夫として、行動経済学の分野で発展してきました。
ナッジは、まるで足元に置かれた道しるべのように、気づけば良い方向に進んでいた、というさりげない誘導を可能にします。今回は、私たちの身近な日常のなかに潜むナッジの仕掛けを5つご紹介しながら、それぞれの背景にある理論と、それが私たちの生活にもたらす意味について考えてみたいと思います。
ヘルシーな選択肢は、手の届くところに
冷蔵庫を開けたとき、目に飛び込んできたのがカットフルーツだったら。あるいはテーブルの上に常備されているのがミニトマトやナッツだったら。その瞬間、何を手に取るかは、すでにある程度決まっているのかもしれません。
これは「選択アーキテクチャ」という考え方に基づいています。選択の自由は保ちつつも、人が“最も自然に選びたくなるような場所”に健康的な選択肢を配置することで、無理なく良い行動へ導くことができます。
お菓子を食べるなとは誰も言っていません。ただ、少し探さなければ見つからない位置に置かれることで、「食べないでおこうかな」という心の隙間が生まれるのです。その小さな“余白”が、行動を少しだけ変えてくれるのかもしれません。
小さな器が、満足感を大きくする
同じ量の食事でも、盛りつける器によってその印象は大きく変わります。小皿にふんわりと盛られた料理と、大皿の片隅に置かれた料理。視覚的なボリューム感が、食べ終えたあとの満足度に不思議と影響してくるのです。
これは「フレーミング効果」と呼ばれる心理現象です。情報の“見せ方”や“受け取り方”が、私たちの判断や感情に影響を与えることを示しています。つまり、減らす努力をするより、見せ方を変えるだけで気持ちが変わるのです。
たとえば、洋服のサイズを変えるように、器をひとまわり小さくしてみる。ほんの少しの変化ですが、自分に優しく寄り添う手段としては、とても自然な一歩ではないでしょうか。
運動のハードルを「あと500歩」に下げる
「毎日30分の運動」と聞くと、少し身構えてしまう方も多いでしょう。でも、「あと500歩だけ多く歩こう」と言われたら、なんとなくできそうな気がしてきませんか?
人は、漠然とした目標よりも、具体的で小さな行動の方が取りかかりやすい傾向にあります。これは「プライミング」と「小さなステップ」の理論に基づいており、たとえばスマホに表示される「今日の歩数」を見るだけでも、その日一日の行動に少しだけ意識が芽生えます。
ほんの少しの積み重ねが、大きな流れをつくる。運動もまた、「特別な何か」ではなく、「日常の中のほんのひと工夫」として捉えてみると、少しずつ景色が変わってくるのかもしれません。
体重計が“問いかけてくる”朝
脱衣所の隅に置かれた体重計と、洗面台の隣にそっと置かれた体重計。どちらが毎日の測定習慣につながりやすいかは、言うまでもありません。
これは「フィードバック」と「リマインダー」の効果を活用したナッジです。見るたびに「今日も測ろうかな?」という気持ちが湧くような、無言のメッセージが視覚的に働きかけてきます。
また、「1週間続けられたらOK」「昨日より100g減っていたら自分を褒めよう」といった小さな目標設定は、続けるためのモチベーションにもなります。数字が語りかけてくる変化に気づいたとき、自分の行動が「見える化」されることで、少しずつ自己信頼にもつながっていく気がします。
忘れかけたころに、家族のひと言が背中を押す
人は一人ではなかなか続けられないけれど、誰かにさりげなく支えられていると、不思議と力が湧いてくることがあります。たとえば、「夜は軽めにしようね」と書かれた冷蔵庫のメモや、「今日もがんばってるね」といった小さな声かけ。これらは、ナッジの中でも「社会的影響力」に基づいた手法です。
注意や命令ではなく、やさしい共感や称賛があることで、人はポジティブな行動を維持しやすくなります。それはまるで、背中を軽くトントンと叩いてくれるような温かさで、知らず知らずのうちに次の一歩を後押ししてくれるのです。
おわりに:行動は「意志」だけじゃないからこそ
私たちはつい、「自分にもっと意志の力があれば」と思いがちですが、実は行動の多くは、意志よりも環境によって形づくられています。ナッジとは、その環境を少しだけ整えてあげること。そしてその工夫は、どれもささやかで、日常の延長線上にあるものばかりです。
だからこそ、無理なく、気負わず、試してみる価値があるのかもしれません。何かを変えたいと思ったとき、「頑張らなきゃ」と力を入れるより、「どんな仕掛けがあれば、自然とできるかな?」と問いかけてみる。そんな視点の切り替えが、あなたの毎日を少しだけ軽やかにしてくれるかもしれません。
次世代マーケティング戦略を無料プレゼント
この記事をお読みいただいた方へ、期間限定の特典をご用意しました。公式LINEにご登録いただくと、以下の豪華特典(すべて無料)を今すぐお受け取りいただけます。
- 「人の心理とビジネスを10年以上研究しつづけた結果 成功するビジネスの作り方まとめ」(動画)
- 「AIに勝てるニューロマーケティング本」(PDF)
- 「私があなただけに教えるAIを使ってマーケティングする方法」(PDF)
- 「黒字から始めるマーケティングのやり方」(PDF)
どれも、経営者やマーケターの皆様にとって明日から実践できるヒントが満載のコンテンツです。LINE登録はわずか30秒で完了しますので、ぜひ友だち登録して特典をお受け取りください!成功するビジネスへのヒントを詰め込んだ資料と動画を手に、新たなマーケティング施策に踏み出してみましょう。
継続的に顧客の心と脳を研究し、賢く脳科学を活用することで、きっとあなたのマーケティングも次のステージへと進むはずです。ぜひこの機会にニューロマーケティングの第一歩を踏み出してください。


法廷臨床心理学博士・ニューロマーケティング(脳科学マーケティング)トレーナー
株式会社ビジネスサイエンスジャパン取締役。ビジネスサイエンストレーニングアカデミー学長。
1985年東京都文京区生まれ。神奈川県横浜市のサン・モール・インターナショナル・スクールの高校を卒業。
2006年米国オレゴン州ルイス&クラーク大学にて心理学専攻及び中国語を副専攻で大学卒業。
2008年米国フロリダ州アルビズ大学大学院にて心理学修士課程修了。
2013年同大学院臨床心理学博士号、法廷特化で卒業(博士論文Doctoral Project:Endo, T. K. (2012) Test Construction: Clinician’s Gay Male Competence Inventory. (Doctoral dissertation, Carlos Albizu University)。後、オレゴン州にて臨床心理学者の国家治療免状を獲得。マイアミ市警、FBI、CIAの調査支援を行った実績を持つ。
2017年には薬物依存人口を減らした功績を称えられ、2017年フロリダ州ジュピター市より表彰される(2017 Best of Jupiter Awards - Drug Abuse & Addiction Center)。現在は実践的ビジネスサイエンス、実践的心理学、脳科学的教育、ニューロマーケティングの普及、後進の育成に努める。著書に『売れるまでの時間-残り39秒 脳が断れない「無敵のセールスシステム」』(きずな出版)、共著に『仕事の教科書』(徳間書店)がある。


