考えすぎて動けない心理と行動への切り替え方
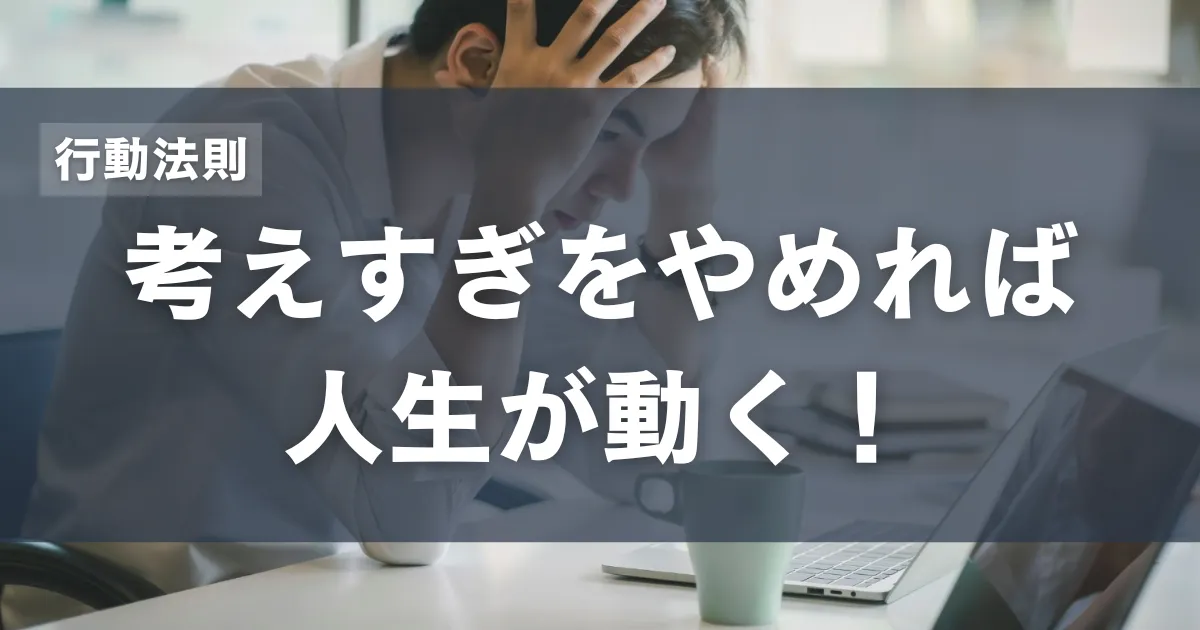
「やらなきゃいけない」と分かっているのに、頭の中で考えすぎて一歩が踏み出せない……
そんな悩みを抱えていませんか?
メールの返信に何時間もかける。新しい挑戦に心が揺れるのに「失敗したらどうしよう」と足がすくむ。頭では分かっているのに体がついてこない。まるで車のエンジンをふかしながら、ブレーキを踏み続けているような状態です。
この記事では「考えすぎ 動けない」という状態の正体を解説します。過剰思考や完璧主義との関係、頭の中で止まる心理、そして行動と思考のズレをどう修正するかを紹介。そして最後には「行動する思考法」を具体的に提示します。
あなたが「止まったままの自分」を卒業して、軽やかに動ける人へと変わるためのヒントを一緒に探していきましょう。
考えすぎて動けないのはなぜか?
頭では理解しているのに体が動かない。
それは決して意志の弱さではなく、脳の仕組みです。
人の脳は未来を予測してリスクを避けるように進化してきました。脳の扁桃体は「危険があるか」を敏感にキャッチし、前頭前野が「どうすれば安全か」を計算します。この働きが強すぎると「行動を止める理由」ばかりを探してしまうのです。
頭の中で止まる心理の特徴
- 最悪のシナリオばかりを想像してしまう
- 起きてもいない未来を繰り返しシミュレーションする
- 行動前に不安を完全に消そうとするが、逆に不安が増える
まるで頭の中で延々と再生される「心配の映画」を観ているように、時間だけが過ぎていきます。

完璧主義と過剰思考の関係
過剰思考を強める背景にあるのが「完璧主義」です。
完璧主義の人は「100点じゃなければ意味がない」と思い込みます。だからこそ「これで十分」とは思えず、行動を先延ばしにしてしまうのです。
完璧主義が招く行動と心理のズレ
- 今やるべきと分かっていても「もっと準備を」と止まる
- 考えすぎて動けず、時間だけが過ぎる
- 行動よりも「不安のコントロール」にエネルギーを使ってしまう
【例】仕事の場面での完璧主義
- プレゼン資料を直し続けて締切直前まで提出できない
- メールを何度も書き直し、送信が遅れる
- 新しい挑戦を「まだ早い」と見送り続ける
心理学の研究でも、完璧主義と不安障害・うつ症状の相関が報告されています。つまり「できない自分を責める」ほど、さらに動けなくなる悪循環に陥るのです。

過剰思考がもたらす悪循環
考えすぎて動けないことは、単なる「遅れ」ではありません。
- 自己肯定感が下がる
- 「またできなかった」と無力感が積み重なる
- 不安が強まり、さらに動けなくなる
さらに社会的にも影響が出ます。会議で意見を言えない、チャンスを逃す、信頼を損なう…。気づけば「行動できない人」というレッテルを自分自身に貼ってしまうのです。
これは、イヤホンのコードが絡まっていくようなもの。解こうとするほど余計に絡み、身動きがとれなくなる悪循環です。
過剰思考から抜け出すための具体的対処法
ではどうすれば「考えすぎて動けない」状態から抜け出せるのでしょうか?
小さな行動で脳をだます
行動は不安の特効薬です。
メールを1文だけ書く、机に資料を広げるなど「一歩」動くだけで、脳は「私はできる」と認識します。
60点ルールを導入する
「まずは60点で出す」と決めると、完璧主義の鎖が外れます。
実際のビジネス現場では、完璧よりも「早さと改善力」が評価されます。
時間制限を設定する
「5分で決める」とタイマーを使うと、思考がダラダラ続くのを防げます。制限がある方が集中力は増すのです。
外に出す習慣
頭の中で考え続けると、不安は膨らみます。
紙に書き出すことで客観視でき、行動に移しやすくなります。
行動する思考法を身につける
大切なのは「考えてから動く」ではなく「動いてから考える」という順番です。
人の思考には「直感的で素早いもの」と「熟考的で慎重なもの」の二つのモードがあります。
動けない人は、慎重なモードに偏りすぎているのです。
【行動思考のポイント】
- 小さなYesを積み重ねる
- 「進んだ事実」を評価する
- 行動後に短く振り返る
歩き出せば霧が晴れるように、不安は自然と小さくなっていきます。
具体例で学ぶ「考えすぎ 動けない」からの脱出
ここでは「仕事」「人間関係」「プライベート」での具体例を挙げます。
仕事の場合
【例】上司への報告メールがなかなか送れない
→ 「誤解されたらどうしよう」と考えすぎて動けなくなる
→→【 解決策】「まず1文だけ書く」「5分で送るルール」を導入する
【例】プレゼン準備に時間をかけすぎる
→ 資料を作り直してばかりで完成が遅れる
→→【 解決策】「まずは骨組みだけ提出し、意見をもらって改善する」
人間関係の場合
【例】友人を誘いたいが「断られたら嫌だ」と考えてしまう
→ 何日も連絡をためらう
→→【 解決策】「結果は相手の自由」と割り切り、簡単なLINEを送る
【例】会議で発言できない
→ 「間違っていたら恥ずかしい」と考えすぎて黙ってしまう
→→【 解決策】「一言だけ意見を言う」と決めて場数を踏む
プライベートの場合
【例】部屋を片付けたいが「どこから始めればいいか」と悩んで動けない
→ 結果的に一日中進まない
→→【 解決策】「机の上だけ」「服10枚だけ」と範囲を小さくして始める
【例】運動を始めたいが「続けられなかったらどうしよう」と悩む
→ 何もせずに日々が過ぎる
→→【 解決策】「1日5分ストレッチ」から始める
こうして「小さく動く仕組み」を作れば、過剰思考は自然に薄れていきます。
ストーリーで学ぶ「動ける自分」への変化
ある起業家は資料作成に時間をかけすぎ、チャンスを逃していました。
しかし「60点ルール」を導入したことで状況は一変。まずは提出し、相手からフィードバックを得ることで改善の速度が増し、結果的に質も上がりました。
別の例では、会社員の女性が「会議で発言できない」ことに悩んでいました。彼女は「毎回一言は意見を言う」と小さなルールを作ったのです。すると徐々に自信がつき、今ではプロジェクトリーダーを任されるまでに成長しました。
動けば未来は変わる。これは誰にでも当てはまる真実です。
おすすめ記事紹介
さらに理解を深めたい方に、遠藤貴則ブログの過去記事をおすすめします。
どちらも「思考と行動のズレ」を修正し、自然に動ける自分をつくるヒントになります。
行動する思考法で未来を変えるために
- 考えすぎて動けないのは「過剰思考」と「完璧主義」が原因
- 対処法は「小さな行動」「60点ルール」「時間制限」「外に出す」
- 行動を優先する「行動思考」が未来を変えるカギ
あなたにはすでに動ける力が備わっています。
この記事を閉じたら、まずはノートを開き「今日の小さな行動」を一つ書き出してみましょう。
その一歩が未来の扉を開きます。
動いた人だけが、不安を越えて自分らしい未来をつかむのです。
だからこそ、今この瞬間に動き出してみませんか。
次世代マーケティング戦略を無料プレゼント
この記事をお読みいただいた方へ、期間限定の特典をご用意しました。公式LINEにご登録いただくと、以下の豪華特典(すべて無料)を今すぐお受け取りいただけます。
- 「人の心理とビジネスを10年以上研究しつづけた結果 成功するビジネスの作り方まとめ」(動画)
- 「AIに勝てるニューロマーケティング本」(PDF)
- 「私があなただけに教えるAIを使ってマーケティングする方法」(PDF)
- 「黒字から始めるマーケティングのやり方」(PDF)
どれも、経営者やマーケターの皆様にとって明日から実践できるヒントが満載のコンテンツです。LINE登録はわずか30秒で完了しますので、ぜひ友だち登録して特典をお受け取りください!成功するビジネスへのヒントを詰め込んだ資料と動画を手に、新たなマーケティング施策に踏み出してみましょう。
継続的に顧客の心と脳を研究し、賢く脳科学を活用することで、きっとあなたのマーケティングも次のステージへと進むはずです。ぜひこの機会にニューロマーケティングの第一歩を踏み出してください。


法廷臨床心理学博士・ニューロマーケティング(脳科学マーケティング)トレーナー
株式会社ビジネスサイエンスジャパン取締役。ビジネスサイエンストレーニングアカデミー学長。
1985年東京都文京区生まれ。神奈川県横浜市のサン・モール・インターナショナル・スクールの高校を卒業。
2006年米国オレゴン州ルイス&クラーク大学にて心理学専攻及び中国語を副専攻で大学卒業。
2008年米国フロリダ州アルビズ大学大学院にて心理学修士課程修了。
2013年同大学院臨床心理学博士号、法廷特化で卒業(博士論文Doctoral Project:Endo, T. K. (2012) Test Construction: Clinician’s Gay Male Competence Inventory. (Doctoral dissertation, Carlos Albizu University)。後、オレゴン州にて臨床心理学者の国家治療免状を獲得。マイアミ市警、FBI、CIAの調査支援を行った実績を持つ。
2017年には薬物依存人口を減らした功績を称えられ、2017年フロリダ州ジュピター市より表彰される(2017 Best of Jupiter Awards - Drug Abuse & Addiction Center)。現在は実践的ビジネスサイエンス、実践的心理学、脳科学的教育、ニューロマーケティングの普及、後進の育成に努める。著書に『売れるまでの時間-残り39秒 脳が断れない「無敵のセールスシステム」』(きずな出版)、共著に『仕事の教科書』(徳間書店)がある。


