ニューロマーケティングで売上3倍を実現“買いたくなる脳”を動かす3つの裏戦略
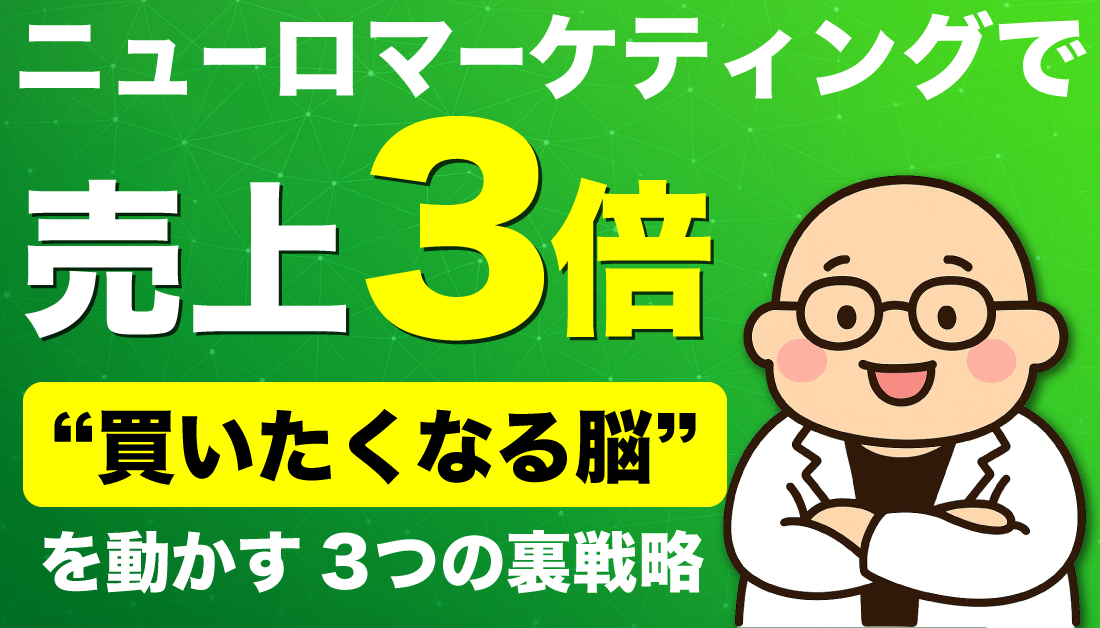
「なんとなく」手に取ってしまった物、つい「欲しいな」と思って買ってしまった物…最近、そんな経験、ありませんか?実はそれ、あなたの理性よりも先に、脳が「欲しい」と感じたサインだったのかもしれませんね。
これは、今の時代を生きる私たちにとって、とても身近な感覚かもしれません。なぜなら、どんなに素晴らしい商品やサービスがあっても、「欲しい」と思われなければ、残念ながら手に取ってもらえないからです。そして、その「欲しい」という気持ちは、私たちの意識できる部分だけでなく、脳の無意識的な反応に大きく左右されているようなのです。
本記事では、ホテルに心理学博士である遠藤高典が、科学的・学術的な視点から、ビジネスや私たちの日常に活かせるヒントを、分かりやすい言葉でお話しできればと思っています。今日のテーマは、まさにそんな「脳が買いたくなる瞬間」を意図的にデザインし、売上を3倍に伸ばしたとあるカフェの、ちょっと面白い裏戦略についてです。ニューロマーケティング(脳科学マーケティング)のエッセンスは、あなたのビジネスや、もしかしたら普段の人間関係にも応用できる可能性があるかもしれません。
売上3倍の秘密は「脳」へのアプローチにあるようです
「なぜか、あのお店には吸い寄せられてしまうんだよなぁ」…そんな風に感じたこと、ありませんか?売上を3倍に伸ばしたというカフェの秘密は、どうやら私たちの「脳」に静かに働きかけるアプローチにあったようです。
今回の事例は、少しユニークな視点からアプローチしてみたお話です。ニューロマーケティングや統合心理学、行動経済学といった分野の知見を借りて、とあるカフェにそっと工夫を加えてみた結果、驚くことに売上が3倍になったというのです。もしあなたが店舗をお持ちだったり、誰かに何かを届けたいサービス業に携わっていたりするなら、きっと何かヒントが見つかるのではないでしょうか。
まず、現代の消費行動を考える上で、少し立ち止まってみたいことがあります。それは、「人は本当に心から『欲しい』と思って物を買っているのだろうか?実は、『欲しくさせられている』側面もあるのではないか?」という視点です。
衣食住のように、生きていく上で欠かせないものは、マズローの欲求階層説で言うところの、比較的下の階層で満たされる基本的な欲求です。現代では、多くの人がこうした最低限の生活を満たせるようになり、本能的な「これがなければ困る」という強い欲求は、少し薄れてきているのかもしれません。
では、私たちは何を基準に物を買っているのでしょう?一見、理性的に考えているように見えて、実はその多くの行動は、私たちの「無意識」、つまり脳の自動反応をうまく引き出された結果だと言われています。成功しているカフェやお店は、単に商品が「美味しい」とか「安い」というだけでなく、お客さんの「買いたくなる」という脳のスイッチを、意図的に、そして巧みに押しているのかもしれません。
そうでないと、どんなに自信のある商品でも、残念ながら見向きもされない、という壁にぶつかってしまうことになります。今の時代、人が何かを買うまでのプロセスは、少し変わってきているのかもしれません。「本能的な直感で『なんかこれ、良さそう!』と感じる」→「心が動いて感情的になる」→「最後に、よし買おう!と論理的に決める」という、まるで3段階のステップを踏むような流れになっているようです。「人は感情で買う」とよく言われますが、その感情さえも、さらに前の「本能」に突き動かされている時代になっている、とも考えられるのではないでしょうか。では、この「本能」に優しく語りかけるには、どうすれば良いのでしょう。
事例:地方の小さなカフェのお話
今回のお話の舞台は、地方にある、ごく普通の小さなカフェです。詳しい場所をお伝えできないのは残念ですが、売上は特に秀でているわけではなく、味も「うん、美味しいね」という、決して悪くはないけれど特別感動するほどでもない、といったレベルだったそうです。お客さんの入りもまばらで、リピーターさんも少ない、そんな状況だったといいます。
そこで、経営者の方にご提案してみたのが、「お客さんの脳が自然と『買いたくなる』ような、お店の環境をちょっとデザインしてみませんか?」という試みでした。
わずか3つの要素に少し手を加えただけで、なんと1ヶ月後には売上が3倍以上に伸び、SNSでも話題になるほどになったそうです。今回は、その「買いたくなる脳を刺激した3つのポイント」を、皆さんにもご紹介したいと思います。これは、飲食店を経営されている方はもちろん、何かを「届けたい」と思っている方なら、試してみる価値は大いにあるのではないでしょうか。
戦略1:香りが呼び覚ます「欲しい」のスイッチ(プライミング効果)
この戦略、実は私たちの身近なところでもよく使われているように感じます。例えば、パン屋さん。焼きたてのパンの、あのたまらない香りが、お店の前の道にふわっと漂ってくるように、換気扇の排気を意図的に道の方向へ向けていることがあるそうですね。あの香りを嗅いだ瞬間、「ああ、焼きたてのパンだ、きっと美味しいに違いない!」と、思わずお店に足を踏み入れたくなる…そんな経験、ありませんか?
私の近所のお茶屋さんでは、あえてお店にほうじ茶を作る機械を置いて、人の通りが多くなる週末には、その場でほうじ茶を焙じるんです。香ばしい匂いがふんわりと漂ってきて、「なんだろう?」と自然と意識がそちらに引き寄せられるんですよね。
なぜ、こんなにも香りが私たちに影響を与えるのでしょう。それは、匂いという情報が、私たちの感情をつかさどる「感情脳」に、とてもダイレクトに繋がっているからだと言われています。もしあなたのビジネスで香りを活用できるなら、これはぜひ試してみていただきたいアプローチの一つです。香りのトリガーは、私たちの心や行動に非常に強く働きかける可能性があるようです。例えば、車メーカーの中には、特定の香りを車内に漂わせることで、ブランドイメージや心地よさを演出しているところもあるといいます。「新車の香り」も、実は意図的に作られているものがあるそうですよ。
では、今回ご紹介するカフェでは何をしたのでしょう?
なんと、店の前に、焙煎したコーヒーの香りをミスト状にして、ふんわりと漂わせてみたのです。
私たちの脳は、香りを通して過去の記憶や感情を呼び起こす力を持っています。味覚も、感情と深く結びついている扁桃体とダイレクトに繋がっていますから、香料によって「美味しいかもしれない」「なんだか落ち着くな」「ちょっと立ち寄ってみようかな」といった、無意識の「プライミング」を起こすことができるわけです。これは心理的な効果としては、感情の引き金となり、自然な行動の意思決定に繋がっていくと考えられます。コーヒー好きな方なら、あの香りを嗅いだだけで、「あ、良い香りだ。ちょっと飲んでみようかな」と、心が動かされるのではないでしょうか。
もし、香りを使うのが難しい場合は、音を活用する方法もあるようです。別のクライアントさんの例ですが、レモネードを売るお店で、お客さんが店の前を通るタイミングで、レモネードを混ぜるシャカシャカという音を立てることで、注意を惹きつけるという工夫をされていたそうです。五感への働きかけは、さまざまな形で応用できる可能性があるのかもしれません。
戦略2:選ばせ方をデザインする心理術(メニューの並び順)
2つ目の戦略は、お客さんの「選び方」を少し変えてみる、というアプローチでした。これは、デフォルトヒューリスティックという考え方に基づいていると言われています。
デフォルトヒューリスティックとは、私たちは提示された選択肢の中で、特に「デフォルト」として設定されているものや、最初に目に飛び込んできたもの、あるいは最初に勧められたものを、無意識のうちに選びやすい傾向がある、という心理的な法則です。選択肢がたくさんあることは、一見魅力的ですが、あまりに多すぎると、かえって選べなくなってしまう…「決定回避の法則」のような現象も起こり得ますよね。
このカフェでは、お店の前や店内に置かれたメニューの並び順に工夫を凝らしました。具体的には、一番見てほしい「人気ナンバーワン」のメニューを、メニュー表の左上に配置したのです。そして、そのすぐ横には「期間限定メニュー」を置いてみました。
私たちの脳は、一番最初に目にした情報(プライマシー効果)や、「今しか手に入らない!」という限定性に、強く反応しやすい性質があるようです。人気ナンバーワンは「みんなが選んでいるなら安心」という社会的な証明になり、期間限定は「逃したら損かも」という希少性を刺激します。
なぜ左上かというと、これは現代の私たちが(特に日本語や英語のような左から横書きの言語に慣れている場合)、つい無意識のうちに左上から視線を動かすことが多い、という目の動き(アイトラッキング)に基づいているそうです。(縦書きの場合はまた変わってきますが、このカフェの場合は横書きのメニューだったのでしょうね。)
このようにメニューを配置することで、お客さんはたくさんの選択肢からイチから考える負担が減り、「人気ナンバーワンか、期間限定か…よし、どっちかにしよう!」と、自然な流れで選ぶことを促されるわけです。これは、お客さんの選択をスムーズにし、ストレスなく「買わざるを得ない」ような気持ちに導く、静かなデザインと言えるかもしれません。ストーリーテリングや視線誘導といった要素を組み合わせた、ちょっとした心理戦略とも言えるかもしれませんね。他のメニューももちろんありますが、それらは「ついでに」とか、お店に慣れた「常連さんがたまに」頼むもの、という位置づけになっていくことが多いようです。
おそらく、多くの飲食店の方が経験として感じられていることと思いますが、「人気ナンバーワン」と書かれたものと「期間限定メニュー」が、圧倒的に良く売れる、という傾向があるようです。これは、お客さんが選ぶものをそっと誘導できるだけでなく、仕入れなどのオペレーションが楽になる、という現実的なメリットにも繋がるのかもしれません。
戦略3:時間帯で心模様を彩る(音楽と照明の調整)
3つ目の工夫は、店内に流れる音楽と、お店を照らす照明を、時間帯によって変えてみた、というものです。これは、リズムと私たちの脳波が共鳴する現象を利用していると考えられます。
例えば、朝の時間帯には、爽やかな気分になれるようなBGMを流し、照明も自然光に近い明るさにする。これは、私たちが活動的になる時に優位になる「ベータ波」という脳波を、心地よく促すように意図しているのかもしれません。そして、夕方以降には、少し落ち着いたジャズのような音楽に切り替え、照明も間接照明のような、温かみのある柔らかな光に変える。これは、リラックスしている時に優位になる「アルファ波」を誘うような環境づくりと言えるでしょう。
このように、時間帯に合わせて脳波の状態に寄り添うような環境をデザインすることで、お客さんは無意識のうちに「なんだかここに長居したくなるな」「もう一杯、お代わりしようかな」といった気持ちになりやすくなるのではないでしょうか。これは、脳科学的な視点から見ると、私たちの脳が最も快適だと感じる「ゾーン」へ、お店側がそっと誘導している、とも考えられます。
ビジネスの視点から見れば、これはお客さんの滞在時間を延ばすこと、つまり一人のお客さんが一生涯でどれだけお店に貢献してくれるかを示す「LTV(顧客生涯価値)」の最大化に繋がる、とても重要な戦略になり得ます。時間帯によって、流す音楽の種類やテンポ、そして照明の色合いや明るさを変えていくことは、お店全体の印象を大きく左右し、お客さんの心に静かに語りかけることになるのかもしれませんね。
まとめ:「売れる」は、もしかしたら偶然ではないのかもしれません
今回ご紹介したカフェのように、「売れる」という状態は、単なる偶然の積み重ねというよりも、むしろ意図的な戦略の結果として生まれることが多いのかもしれません。
先ほどもお話ししたように、私たちの購買行動は、一見複雑に見えて、「本能的なひらめき」→「心が動く感情」→「最後に理性的な判断」という、ある種の自然な流れで発生するようです。そして、その一連の購入体験が、私たちの記憶の中に刻み込まれていきます。
今回のカフェの事例をこの流れに当てはめてみると、
- 「感情」を動かすために:お店の前の心地よい香り、そして店内の気分を盛り上げる音楽や照明が、私たちに静かに働きかけていたのでしょう。
- 「行動」(意思決定)をスムーズにするために:脳が選びやすいようにデザインされたメニューの配置や、選び方をそっと促す工夫(選択設計)が施されていたのです。
- そして、「記憶への定着」に関しては:(これは元々ある程度されていたそうですが)また来たいなと思わせるリピーター施策や、SNSでの発信を促す仕掛け、お得なクーポンの配布などが、今回の体験を良い記憶として残し、次回の来店に繋げていたと考えられます。
もしあなたが、今何かを「届けたい」と思っているなら、ぜひ一度、五感に働きかける仕掛けや、お客さんの「選び方」を少しデザインしてみるという視点を取り入れてみてはいかがでしょうか。きっと、あなたのビジネスに新しい風を吹き込むヒントが見つかるかもしれませんね。
次世代マーケティング戦略を無料プレゼント
この記事をお読みいただいた方へ、期間限定の特典をご用意しました。公式LINEにご登録いただくと、以下の豪華特典(すべて無料)を今すぐお受け取りいただけます。
- 「人の心理とビジネスを10年以上研究しつづけた結果 成功するビジネスの作り方まとめ」(動画)
- 「AIに勝てるニューロマーケティング本」(PDF)
- 「私があなただけに教えるAIを使ってマーケティングする方法」(PDF)
- 「黒字から始めるマーケティングのやり方」(PDF)
どれも、経営者やマーケターの皆様にとって明日から実践できるヒントが満載のコンテンツです。LINE登録はわずか30秒で完了しますので、ぜひ友だち登録して特典をお受け取りください!成功するビジネスへのヒントを詰め込んだ資料と動画を手に、新たなマーケティング施策に踏み出してみましょう。
継続的に顧客の心と脳を研究し、賢く脳科学を活用することで、きっとあなたのマーケティングも次のステージへと進むはずです。ぜひこの機会にニューロマーケティングの第一歩を踏み出してください。


法廷臨床心理学博士・ニューロマーケティング(脳科学マーケティング)トレーナー
株式会社ビジネスサイエンスジャパン取締役。ビジネスサイエンストレーニングアカデミー学長。
1985年東京都文京区生まれ。神奈川県横浜市のサン・モール・インターナショナル・スクールの高校を卒業。
2006年米国オレゴン州ルイス&クラーク大学にて心理学専攻及び中国語を副専攻で大学卒業。
2008年米国フロリダ州アルビズ大学大学院にて心理学修士課程修了。
2013年同大学院臨床心理学博士号、法廷特化で卒業(博士論文Doctoral Project:Endo, T. K. (2012) Test Construction: Clinician’s Gay Male Competence Inventory. (Doctoral dissertation, Carlos Albizu University)。後、オレゴン州にて臨床心理学者の国家治療免状を獲得。マイアミ市警、FBI、CIAの調査支援を行った実績を持つ。
2017年には薬物依存人口を減らした功績を称えられ、2017年フロリダ州ジュピター市より表彰される(2017 Best of Jupiter Awards - Drug Abuse & Addiction Center)。現在は実践的ビジネスサイエンス、実践的心理学、脳科学的教育、ニューロマーケティングの普及、後進の育成に努める。著書に『売れるまでの時間-残り39秒 脳が断れない「無敵のセールスシステム」』(きずな出版)、共著に『仕事の教科書』(徳間書店)がある。


