ニューロマーケティングとは?ビジネスに役立つ消費者心理・脳科学活用の基本と視線戦略
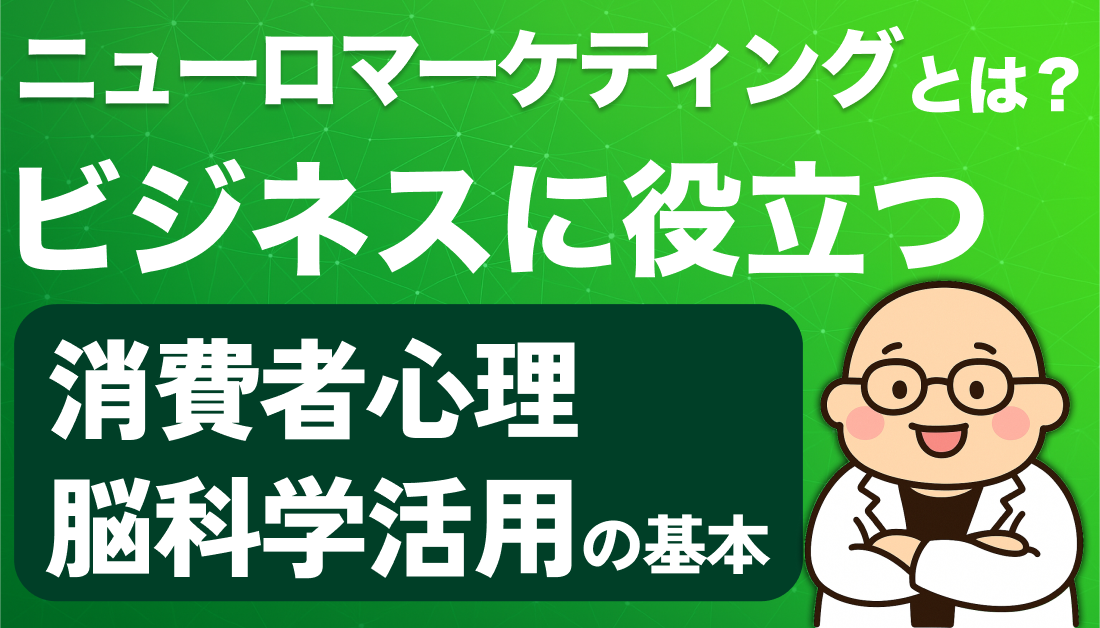
お客様の心をつかむには、どうすればいいのか?この問いに対する新たなヒントが、脳科学の知見を応用した「ニューロマーケティング」にあります。人の意思決定の多くは無意識に行われており、その背後には感情や記憶、視覚、さらには脳波や視線の動きといった消費者心理を左右する要素が影響しています。
本記事では、中小企業でも実践できるニューロマーケティングの基本から応用までを、豊富な事例を交えて解説。理論だけでなく、すぐに使える心理戦略を知ることで、あなたのビジネスに新たな成果をもたらすヒントが見つかるでしょう。
ニューロマーケティングとは何か?脳科学とマーケティングの融合
近年、従来のマーケティング手法では届かない“無意識”の領域にアプローチする方法として注目されているのが「ニューロマーケティング」です。
消費者の意思決定の多くが脳の自動反応によって行われているという前提のもと、脳科学とマーケティングを融合させたこの手法は、中小企業にとっても効果的な武器となり得ます。まずはその定義や背景、そして現代における重要性について解説します。
ニューロマーケティングの定義と背景
ニューロマーケティングとは、脳科学(神経科学)とマーケティングの知見を融合させた新しい手法です。
具体的には、消費者が広告や商品に接したときに脳がどのように反応するかを、脳波やfMRI(機能的磁気共鳴画像法)などのツールを使って可視化し、無意識下の購買動機や意思決定のプロセスを明らかにします。
近年では、脳波測定や視線追跡といった技術が進化し、消費者の潜在的な反応を、より精密に分析できるようになっています。
従来のマーケティングはアンケートやグループインタビューといった手法を使って、消費者の「言葉」に依存してきましたが、これらは本音と建前が混在しやすく、正確な意図をつかみにくいという課題がありました。
ニューロマーケティングはその点で、行動の裏にある「脳の本音」に直接アプローチするため、より信頼性の高いインサイトが得られます。
たとえば、ある商品パッケージに対して視線がどこに集中し、どの色に反応が強く、どの瞬間に「欲しい」と感じたのかなど、言語化できない感情の動きを科学的に分析できます。
こうしたデータを活用すれば、広告の最適化や商品設計、ブランド戦略の精度が飛躍的に高まり、中小企業にとっても競争優位性を築くための有効な武器となるでしょう。
脳科学で読み解く購買行動の仕組み
人間の購買行動は、思考よりも感情や直感によって左右されていることが、脳科学の研究から明らかになりました。
たとえば、私たちが「この商品が欲しい」と思う瞬間、脳内では扁桃体や前頭前野、報酬系と呼ばれる領域が活発に反応しています。
扁桃体は感情処理を担い、好奇心や快感、不安などに関連し、前頭前野は意思決定や価値判断をつかさどる領域です。そして報酬系は「得をする」「うれしい」という感覚をもたらすドーパミンの分泌を誘発します。これらの脳の動きは一瞬のうちに起こり、私たちはその結果として「買おう」という判断を下しているのです。
さらに、視覚や聴覚など五感からの情報も脳に強く影響を与えます。とくに視覚情報は判断において重要な役割を果たし、パッケージデザインや広告ビジュアルの印象が購買意欲に直結することが多いのです。
脳科学の知見を採り入れることで、どのような色、形、言葉が人の感情を動かすのかを科学的に理解できます。そして、より効果的なマーケティング施策の立案につながります。中小企業であっても、消費者が無意識にどのように反応するかを知ることで、商品設計や販売促進の戦略に活用できるでしょう。
ニューロマーケティングが注目される理由
ニューロマーケティングが現在、急速に注目を集めている背景には、消費者の購買行動が従来の理論では説明しきれないという課題があります。
SNSやスマートフォンの普及により、現代人の情報接触量は飛躍的に増え、まさに「情報過多」の時代です。1日に数千件の広告や情報にさらされる中で、消費者はすべてを論理的に処理することは不可能であり、無意識下の直感や感情に基づいた「無意識の意思決定」がますます主流になっています。
そのため、脳の反応や心理メカニズムに直接アプローチできるニューロマーケティングは、マーケティング施策の精度を高めるうえで有効な手段として注目されているのです。
最近では、AI活用により、顧客の反応データや行動履歴を自動的に解析し、パーソナライズされたマーケティング施策へと発展しています。たとえば、「クラウドベースのヒートマップツール」や「行動ログを可視化するSaaS型の解析サービス」が登場しました。
実際に、中小企業がアクセス解析やA/Bテストを採り入れて成果を上げている事例も増えています。これにより、大企業だけでなく中小企業でもニューロマーケティングの知見を実践に採り入れることが、ツール・知識両面で現実的な選択肢となってきたのです。
また、デジタル広告のクリック率やサイトの離脱率など、具体的な数値で効果検証できる点も、経営判断において重要な材料となっています。つまり、「感覚に頼るマーケティング」から「科学に基づくマーケティング」へと進化する中で、ニューロマーケティングは新時代の必須知識として注目されているのです。
さらに、技術面の進化も大きな要因です。かつては高額だった脳波測定機器や視線追跡装置が手頃な価格で利用できるようになり、研究結果や事例も豊富に公開されています。これにより、大企業だけでなく中小企業でも、ニューロマーケティングの知見を実践に採り入れることが現実的になってきました。
また、デジタル広告のクリック率やサイトの離脱率など、具体的な数値で効果検証できる点も、経営判断において重要な材料となっています。つまり、「感覚に頼るマーケティング」から「科学に基づくマーケティング」へと進化する中で、ニューロマーケティングは新時代の必須知識として注目されているのです。
中小企業が知っておくべき購買心理の基本原則
購買行動は合理的な判断のように見えて、実はその多くが無意識の心理によって動かされています。とくに中小企業にとっては、大手のような潤沢な予算を使わずとも「人間心理」に訴えることで成果を上げることが可能です。
ここでは、購買心理の基礎と中小企業が注目すべきポイントを解説します。
消費者行動はなぜ無意識に左右されるのか
私たちは自分の意思で「これを買おう」と決めていると思いがちですが、実際にはその多くが無意識のうちに決定されています。
脳科学の研究によると、人間の意思決定の最大95%は無意識に行われているとされ、脳は膨大な情報を効率的に処理するために、直感や感情に頼る「ヒューリスティック(簡易判断)」を用いています。
たとえば、店舗で目に入った商品のパッケージにひかれたり、誰かが使っている様子を見て「なんとなく良さそう」と感じたりするのも、すべてこの無意識の働きによるものです。
このような脳の仕組みを理解することで、マーケティングのアプローチも大きく変わります。単に商品スペックや価格を伝えるだけではなく、視覚的な魅力や共感を得るストーリー、感情に訴える表現などを重視することで、消費者の無意識に働きかけることが可能になります。
また、無意識の判断は繰り返しによって強化されるため、広告やブランドの露出頻度を高めることも効果的です。つまり、無意識こそが購買行動の鍵を握っており、その領域に届くメッセージを届けられるかどうかが、マーケティング成功の分かれ道になるのです。
中小企業における心理トリガーの重要性
中小企業が限られたリソースで成果を上げるためには、「心理トリガー」の活用が欠かせません。心理トリガーとは、消費者の心を動かし、購買行動を引き起こす無意識のスイッチのようなものです。
代表的なものには「希少性」「限定感」「社会的証明」「一貫性」「好意」「権威」などがあり、行動経済学の分野でも広く研究されています。これらのトリガーは、広告や商品訴求の中に巧みに織り交ぜることで、自然な形で消費者の行動を誘導でき、購買意欲を高める強力な販売促進手段にすることが可能です。
たとえば「今だけ」「残りわずか」といった希少性の訴求は、「手に入れられないかもしれない」という不安を引き出し、購入を急がせます。あるいは「多くの人が選んでいます」という社会的証明の表現は、「自分も選ぶべきだ」という安心感や信頼感を与えるでしょう。
中小企業がこれらの心理的要素を理解し、訴求メッセージや販売戦略に採り入れることで、予算をかけなくても購買率向上につながります。とくに競合が多い市場では、商品自体の差別化が難しいケースも多いため、「どのように伝えるか」がより重要になってきます。心理トリガーを活用することは、中小企業がマーケティングの成果を最大化するための鍵なのです。
行動経済学と組み合わせた理解の深め方
ニューロマーケティングをより深く理解し、実践に生かすためには、行動経済学との組み合わせが非常に有効です。行動経済学は、実際の人間の行動に基づいて経済活動を分析する学問であり、理論上の「合理的な人間像」では説明しきれない現実の購買行動を明らかにします。
たとえば、「損失回避の法則」は、人は利益を得るよりも損失を避けることに強く反応する傾向があるというもので、これを応用すれば「今買わないと損するかもしれません」といった訴求が有効になります。
また、「選択のパラドックス」も代表的な概念です。選択肢が多いほど満足度が下がり、行動を先送りにしてしまう傾向があるため、商品ラインナップを絞り込んだり、最適な選択肢をあらかじめ提案したりすることで購買率を高められます。
これらの心理的メカニズムは、ニューロマーケティングの観点から見ると、脳の負荷や報酬系の反応とも一致しており、相互に補完し合う関係です。
中小企業がこのふたつのアプローチを融合させてマーケティング施策を設計することで、顧客の無意識に届く精度の高いコミュニケーションが可能になります。科学的根拠に基づいた説得力ある訴求は、顧客の信頼を得やすく、長期的なファン獲得にもつながるでしょう。
中小企業が今すぐ実践できる5つのニューロマーケティング戦略
理論としての理解を深めた後は、実際にどう活用するかが重要です。ここでは、ニューロマーケティングのエッセンスを採り入れた5つの実践的な手法を紹介します。心理トリガーや感情訴求など、すぐに採り入れられる工夫が満載です。
希少性と限定性を生かす「今だけ」戦略
「今だけ」「数量限定」「残りわずか」。こうした言葉に私たちが思わず反応してしまうのは、脳が希少なものに強く価値を感じるようにできているからです。
これは「希少性の原理」と呼ばれる心理現象で、人は手に入りにくいものに対して無意識のうちに高い価値を見いだします。たとえば、商品が多くある棚の中で「あと2個です」と表示されたものに目がいった経験はないでしょうか?これは「FOMO(Fear of Missing Out)」、すなわち「逃したくない」という感情が購買意欲を刺激しているのです。
中小企業にとっても、この希少性や限定性は非常に有効なマーケティング手段です。たとえば「今週末限定セール」「季節限定カラー」「地域限定商品」などは、顧客に「今行動しなければ手に入らないかもしれない」と思わせる効果があります。
たとえば、ストリートブランドとして知られる米国の「シュプリーム(Supreme)」は、意図的に在庫数を絞ることで「即完売」を演出し、希少性の心理を巧みに活用して支持を集めています。
ただし、頻繁に希少性を演出しすぎると、信頼を損なうリスクがあるので注意が必要です。本当に特別なタイミングで限定感を持たせることがポイントです。中小企業でも在庫数の表示や「限定〇〇名」などの工夫により、少ない予算でも購買行動を促す戦略が実行できます。
色彩心理:色が売上に与える意外な影響
色は視覚情報の中でもとくに強力な要素であり、消費者の感情や行動に大きな影響を与えます。ある研究では、人が商品を見た際の第一印象のうち、最大90%が色に基づいて判断されているとされています。
これはつまり、どれだけ優れた商品でも、色の選び方を誤れば、その魅力を伝えられない可能性があるのです。たとえば、赤は緊急性や情熱、食欲を刺激する色として知られ、多くの飲食店やセールの告知に使われています。一方で、青は信頼感や冷静さを連想させるため、銀行や医療、IT業界でよく用いられます。
中小企業においても、色彩心理を生かすことで大きな成果を挙げられるでしょう。たとえば、「安心感を与えたい商品であれば青や白を基調にしたパッケージを採用する」「注目を集めたいボタンには黄色やオレンジを使う」など、色の選択が意図的なメッセージ伝達手段になります。
また、ブランド全体の印象を統一させるために、ロゴやウェブサイトの配色を一貫させることも重要です。視覚的に訴える力を最大限に生かすには、単なるデザインの好みではなく、ターゲットの感情に届く「色の戦略」を立てることが不可欠です。
社会的証明:他人の評価が判断基準になる理由
人は、自分の判断に自信がないとき、他人の行動や意見を参考にして意思決定をする傾向があります。これを「社会的証明」と呼び、マーケティングの現場でも非常に強力な武器として活用されています。
たとえば、飲食店の外に行列ができていると「このお店はおいしいに違いない」と感じたり、通販サイトでレビュー評価が高い商品に安心感を覚えたりした経験はないでしょうか。これは、自分の判断よりも“みんなが選んでいる”という事実に無意識のうちに従ってしまう、社会的証明の効果です。
中小企業がこの心理を生かすには、実際の購入者の声や体験談、導入事例などを積極的に発信することが重要です。顧客の口コミやレビュー、SNSでのシェア、写真付きの投稿などは、新規の見込み客にとって大きな安心材料になります。
また、ECサイトでは「〇人が購入」「現在〇人が閲覧中」といったリアルタイム表示を加えることで、消費者の行動を後押しできます。社会的証明は、自社の実績を可視化することにより、信頼を醸成し、コンバージョン率を向上させる効果が期待できるでしょう。
信頼できる第三者の評価があるだけで、商品やサービスへの抵抗感は大幅に下がり、より多くの顧客を獲得するチャンスが広がるのです。
感情訴求で購買意欲を高める方法
私たちは普段、物を買うときに「論理的に判断している」と思いがちですが、実際には感情が購買の意思決定に大きく影響しています。
脳科学や心理学の研究によれば、人は感情に動かされたときの方が、記憶にも残りやすく、行動にもつながりやすいことが分かっています。たとえば、商品のスペックや価格を丁寧に説明するよりも、「その商品を使った未来の自分がどう感じるか」を描いたストーリーの方が、心に響くのです。
感情訴求にはさまざまな切り口があります。共感を得るエピソード、思わず笑ってしまうユーモア、懐かしさを呼び起こす表現、あるいは問題や不安を代弁するようなメッセージ。
とくに効果的なのは、顧客が抱えている「痛み」にフォーカスし、それを解決できる手段として商品やサービスを提示する方法です。人は利益を得ることよりも、損失を避けることに強く反応します。そのため、「これを逃すと損をする」という形で訴えると反応率が高まります。
中小企業でも感情訴求を効果的に採り入れることで、大手に負けない強いブランドイメージを築くことが可能です。地元に根ざしたストーリーや、実際の顧客との心温まるエピソードをSNSなどで発信することで、顧客とのつながりを深め、信頼を育てられます。
感情に訴えるマーケティングは、単なる販促手段ではなく、長期的なファンづくりに直結する重要な戦略なのです。
中小企業でも取り組める低コスト実践法
ニューロマーケティングというと、脳波測定やMRIといった高度な機器が必要だと思われがちですが、実際には中小企業でも手軽に実践できる方法が数多くあります。重要なのは、脳科学や心理学の知見を理解したうえで、それを日常のマーケティング活動に応用することです。
たとえば、ウェブサイトのボタン文言を「無料で体験」から「今すぐ体験」に変えるだけでも、行動を促す力が変わってきます。これは、緊急性と直接的な行動喚起を意識した言葉の選び方で、脳に刺激を与えられます。
また、商品ページにレビューや「使用者の写真を掲載する」「期間限定のポップを貼る」「色使いを見直す」といった工夫も、ほとんどコストをかけずに実践できる施策です。さらに、感情を喚起するようなキャッチコピーや、地元密着型のストーリーをSNSで発信するのも有効です。
A/Bテストを活用すれば、実際のユーザーの反応を見ながら改善が可能になり、成功確率を高められます。このように、ニューロマーケティングは「高額なツールを使うこと」ではなく、「人間の脳の働きと感情を意識して伝えること」が本質です。
日々のマーケティング施策に小さな工夫を積み重ねるだけで、顧客の反応は大きく変わります。中小企業だからこそ、柔軟かつスピーディーにこうしたアプローチを採り入れやすく、他社との差別化にもつながるといえるでしょう。
成果を最大化するための導入ステップと注意点
ニューロマーケティングの効果を最大限に引き出すには、単なる知識ではなく実践と検証のサイクルが不可欠です。ここでは、自社に合った施策の設計から効果測定、そして改善につなげるための基本ステップを解説します。
自社商品にあわせた心理訴求の設計
ニューロマーケティングを中小企業が実践する際、最も重要なのは「誰に何をどう伝えるか」を明確にすることです。つまり、自社の商品やサービスにあわせて、どの心理トリガーが最も有効に働くのかを見極める必要があります。
たとえば、価格よりも品質で勝負する商品であれば、「信頼」や「権威」を訴求する方が効果的ですし、数量が限られている商品であれば「希少性」や「限定性」を前面に出すことで、購入を後押しできます。
この設計にあたっては、まず自社のペルソナ(理想的な顧客像)を明確にすることからはじめましょう。そのうえで、「その人が感じている不安や欲求は何か?」「どうすれば感情が動くか?」を丁寧に分析し、それに応じた言葉やビジュアルを用いることがポイントです。
商品紹介ページにしても、事実を並べるだけでなく、「この商品を使えばあなたの悩みがどう解決されるか」というストーリーを提示することで、より深く心に響く訴求が可能になります。
また、BtoB商材であっても感情訴求は有効です。意思決定者もまた人間であり、信頼感や安心感、共感に基づいて判断を下しています。自社商品・サービスの本質的な価値を心理的なフレームに落とし込むことは、単なるテクニックにとどまらず、ブランディングや顧客体験の向上にもつながる重要な戦略なのです。
A/Bテストを活用した検証と改善の実践法
ニューロマーケティングの知見を実践的に生かすためには、効果検証が欠かせません。その中でも最も手軽で確実な方法がA/Bテストです。
A/Bテストとは、同じコンテンツにおいて異なる要素(コピー・ボタン色・画像・レイアウトなど)を複数パターン用意。そして、どちらがより高い成果(クリック率、購入率、登録数など)を挙げるかを比較する検証方法です。
直感に頼らず、実際の顧客行動に基づいた意思決定ができるため、中小企業にとっても効果的かつリスクの少ない施策として活用されています。
たとえば、同じ商品でも「今すぐ申し込む」と「このチャンスを逃さないで!」というボタン文言を比べるだけで、反応が大きく異なるケースもあります。これは、言葉が脳に与える印象や感情が異なるためです。
ほかにも、「画像の違い」「ページ構成の順番」「価格表示の方法」など、検証できるポイントは多岐にわたります。重要なのは、一度に多くを変えすぎず、1つずつ変更して結果を測定することです。そうすることで、どの要素が効果に直結しているのかを明確にできます。
A/Bテストを繰り返すことで、顧客が無意識のうちに好むデザインや言葉の傾向、感情的に引かれる要素が徐々に明らかになります。これにより、自社に最適な表現や構成がデータに基づいて導き出せるようになり、マーケティングの成功率を着実に高められるのです。
高額なツールを使わずとも、Google Optimizeなどの無料ツールを活用すれば、小規模な企業でも簡単にテスト環境を構築できます。A/Bテストは、ニューロマーケティングを「勘」ではなく「科学」で進化させる第一歩です。
成果を持続させるPDCAの活用方法
ニューロマーケティングの成果を一過性のものにせず、継続的な成長につなげるには、PDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)の活用が欠かせません。マーケティング施策も一度実施して終わりではなく、常に効果を測定し、改善し続けるプロセスが重要です。
たとえば、感情訴求のキャッチコピーを採用した結果、どのくらいコンバージョン率が向上したのか。A/Bテストで得たデータを基に次の施策をどう設計するか。こうした振り返りと調整の積み重ねが、確実な成果の蓄積を生み出すのです。
PDCAの第一ステップである「Plan(計画)」では、誰に何をどう伝えるかを明確にしたうえで、心理トリガーや行動経済学の要素を設計に組み込みます。次の「Do(実行)」では、実際に広告を出稿したり、Webページを公開したりしてユーザーの反応を観察。
そして「Check(評価)」の段階で、コンバージョン率やクリック率、滞在時間などの指標を基に施策の有効性を測定。最後に「Act(改善)」で、得られたデータをもとに改善策を立て、次回施策に反映させていきます。
このように、PDCAを回し続けることで、自社に最適なマーケティングスタイルが少しずつ見えてきます。とくに中小企業の場合、変化に柔軟に対応できる点が強みです。大企業のように大規模な変更はできなくても、スピード感を持って仮説検証を繰り返すことで、地に足のついた戦略が構築できます。
ニューロマーケティングを導入するだけでなく、PDCAと組み合わせて運用することが、成果を最大化するための鍵となるのです。
ニューロマーケティングで中小企業が変わる理由と未来展望
変化の激しいビジネス環境において、中小企業が持続的に成長するには柔軟な発想と科学的なアプローチが求められます。ニューロマーケティングは、そうした課題に応える力を持つ手法です。今後の可能性と、未来を見据えた活用のヒントを紹介します。
ニッチ市場に勝つための戦略的アプローチ
中小企業が大手と同じ土俵で勝負するのは難しいかもしれませんが、ニッチ市場であれば十分に勝機があります。そこで鍵となるのが、ニューロマーケティングを活用した差別化戦略です。
ニッチ市場では、特定の顧客層の細かなニーズに応えることが重要であり、そこに無意識への訴求を採り入れることで、他社にはない独自の価値を提供できます。たとえば、地元密着型の食品店が「おふくろの味」や「懐かしい香り」といった感情に訴える言葉を使えば、大手にはない「心のつながり」を演出することが可能です。
さらに、ニッチ市場ではターゲットが明確であるため、心理トリガーをより精緻に設計しやすいというメリットがあります。特定の属性に刺さる色や言葉、ストーリーを使って商品やサービスを訴求することで、共感と信頼を生み出せます。
また、競合が少ないため、SNSや口コミでの情報拡散も効果的に機能。中小企業は顧客との距離が近いため、脳科学に基づいた施策をスピーディーに実行し、反応を見ながら柔軟に調整しやすいという利点があります。
このように、ニューロマーケティングは、大規模な市場での勝負に限らず、むしろニッチ市場においてこそ真価を発揮します。顧客の無意識に寄り添い、感情を動かすストーリーと体験を提供することで、競争優位を築き、持続的な成長につなげられるのです。
共感マーケティングで顧客との信頼関係を築く方法
現代のマーケティングでは、単に商品やサービスのスペックを伝えるだけでは不十分です。とくに中小企業にとっては、顧客との「共感」を築くことが、信頼関係を深めるための重要な戦略になります。
共感マーケティングとは、顧客の価値観や悩みや不安・希望などに寄り添い、「まるで自分のことを分かってくれている」と感じさせるような訴求手法です。これはニューロマーケティングの視点から見ると、脳の共感回路や報酬系を刺激し、ポジティブな感情と結びつく体験が生み出されたことを意味します。
たとえば、自社の創業ストーリーに「お客様の声から誕生した商品」や「家族の健康を守るために開発された」という背景を盛り込むだけで、読み手にとって親近感のある存在となります。また、SNSやメールマガジンなどを通じて、顧客の意見に対する返信や紹介、感謝の言葉を発信することも有効です。
これにより、企業と顧客の関係は一方通行ではなく“対話”になり、顧客ロイヤルティの向上にもつながるのです。
共感は人間関係の中でも最も深い信頼を生む要素のひとつであり、それは企業と顧客の関係にも同様に当てはまります。大手にはまねできない「人と人とのつながり」を強みに変えられる中小企業だからこそ、共感を軸としたマーケティングが効果を発揮します。
これにより、価格競争に巻き込まれることなく、長期的なファンを獲得するブランドづくりが可能になるのです。
ニューロマーケティングの未来と中小企業の可能性
ニューロマーケティングの活用は今後ますます広がっていくと予想されます。その理由のひとつが、AIやビッグデータとの融合です。たとえば、Web上での顧客行動や購買履歴、反応傾向をAIが解析し、個々の顧客に最適なコンテンツや訴求方法をリアルタイムで提示する「1to1マーケティング」が実現しやすくなっています。
これは、脳の反応を予測して「どのような言葉やビジュアルに反応しやすいか」をアルゴリズムが把握。そして、顧客一人ひとりにパーソナライズされた顧客体験を提供するという進化形のマーケティングであり、デジタル戦略の要です。
このような最先端技術は一見、大企業にしか手が届かないように思われがちですが、実はクラウドサービスやSaaSツールの普及により、中小企業でも導入しやすくなってきました。
たとえば、メールマガジン配信ツールで顧客の行動履歴に応じて内容を自動的に変化させたり、ヒートマップ分析でウェブサイトの改善ポイントを可視化したりするなど、手軽にはじめられる選択肢は多く存在します。
また、Z世代やミレニアル世代のように「感情重視」「共感重視」の価値観を持つ消費者が主役になる時代には、無意識への訴求がより重要になってくるでしょう。彼らは情報に敏感で、押しつけがましい広告よりも「自分に合っている」と感じられるブランドに心を開きます。
ニューロマーケティングはそうした心の動きに対応するうえで欠かせない視点です。中小企業こそ、柔軟性とスピードを武器に、こうしたトレンドを積極的に採り入れることで、時代の先を行くブランドづくりが可能になります。
次世代マーケティング戦略を無料プレゼント
この記事をお読みいただいた方へ、期間限定の特典をご用意しました。公式LINEにご登録いただくと、以下の豪華特典(すべて無料)を今すぐお受け取りいただけます。
- 「人の心理とビジネスを10年以上研究しつづけた結果 成功するビジネスの作り方まとめ」(動画)
- 「AIに勝てるニューロマーケティング本」(PDF)
- 「私があなただけに教えるAIを使ってマーケティングする方法」(PDF)
- 「黒字から始めるマーケティングのやり方」(PDF)
どれも、経営者やマーケターの皆様にとって明日から実践できるヒントが満載のコンテンツです。LINE登録はわずか30秒で完了しますので、ぜひ友だち登録して特典をお受け取りください!成功するビジネスへのヒントを詰め込んだ資料と動画を手に、新たなマーケティング施策に踏み出してみましょう。
継続的に顧客の心と脳を研究し、賢く脳科学を活用することで、きっとあなたのマーケティングも次のステージへと進むはずです。ぜひこの機会にニューロマーケティングの第一歩を踏み出してください。


法廷臨床心理学博士・ニューロマーケティング(脳科学マーケティング)トレーナー
株式会社ビジネスサイエンスジャパン取締役。ビジネスサイエンストレーニングアカデミー学長。
1985年東京都文京区生まれ。神奈川県横浜市のサン・モール・インターナショナル・スクールの高校を卒業。
2006年米国オレゴン州ルイス&クラーク大学にて心理学専攻及び中国語を副専攻で大学卒業。
2008年米国フロリダ州アルビズ大学大学院にて心理学修士課程修了。
2013年同大学院臨床心理学博士号、法廷特化で卒業(博士論文Doctoral Project:Endo, T. K. (2012) Test Construction: Clinician’s Gay Male Competence Inventory. (Doctoral dissertation, Carlos Albizu University)。後、オレゴン州にて臨床心理学者の国家治療免状を獲得。マイアミ市警、FBI、CIAの調査支援を行った実績を持つ。
2017年には薬物依存人口を減らした功績を称えられ、2017年フロリダ州ジュピター市より表彰される(2017 Best of Jupiter Awards - Drug Abuse & Addiction Center)。現在は実践的ビジネスサイエンス、実践的心理学、脳科学的教育、ニューロマーケティングの普及、後進の育成に努める。著書に『売れるまでの時間-残り39秒 脳が断れない「無敵のセールスシステム」』(きずな出版)、共著に『仕事の教科書』(徳間書店)がある。


